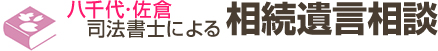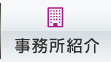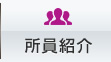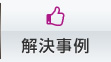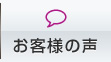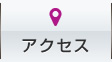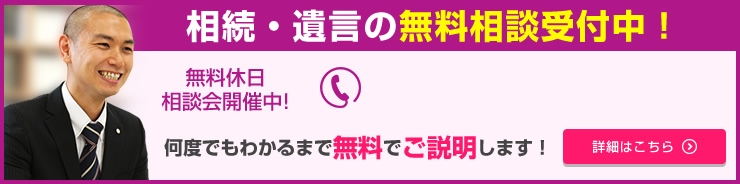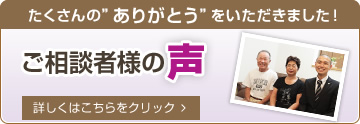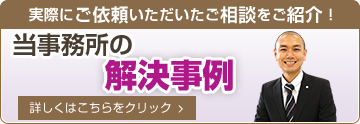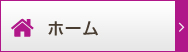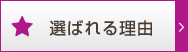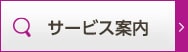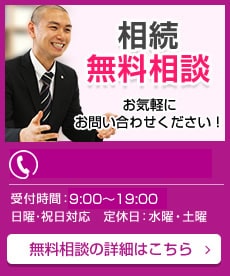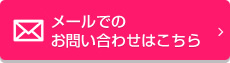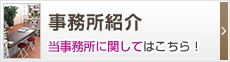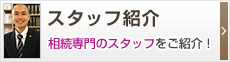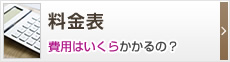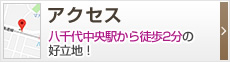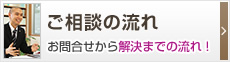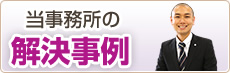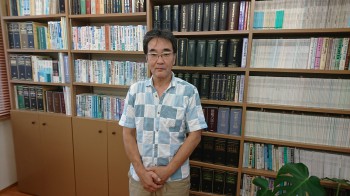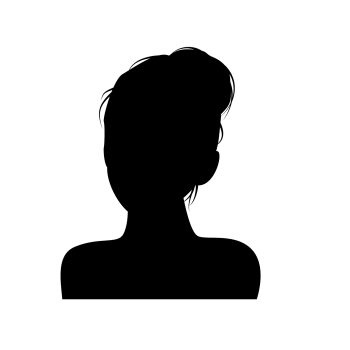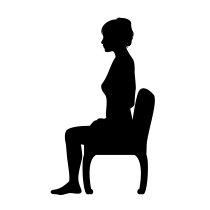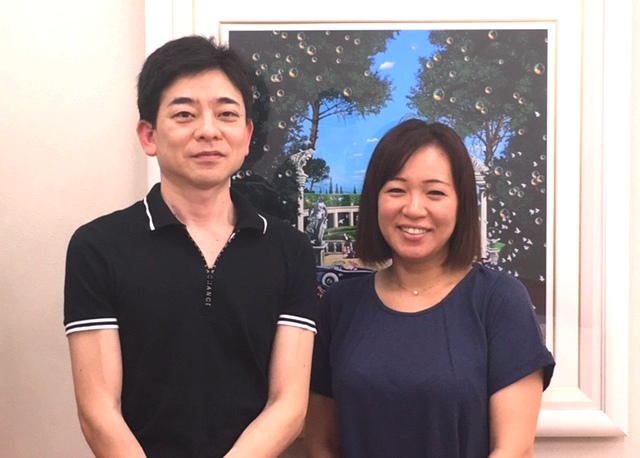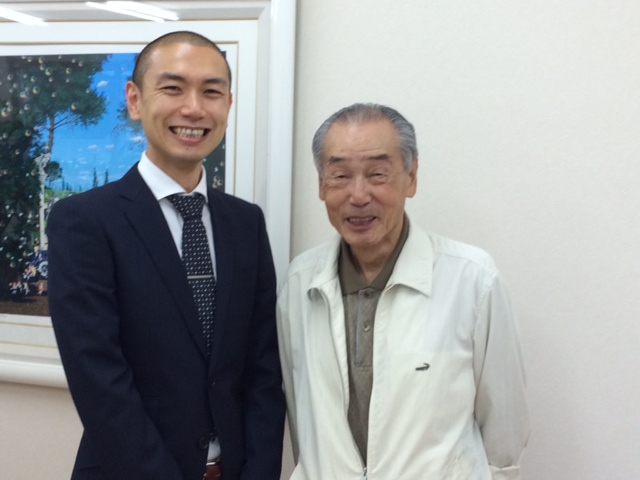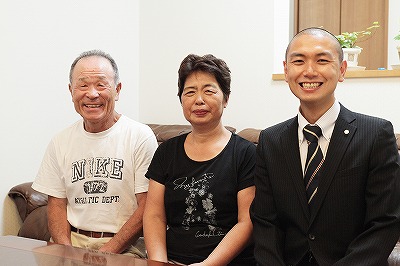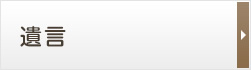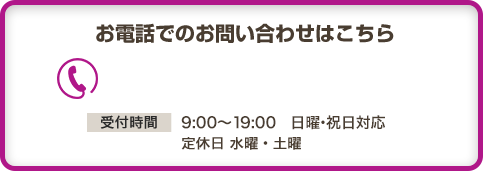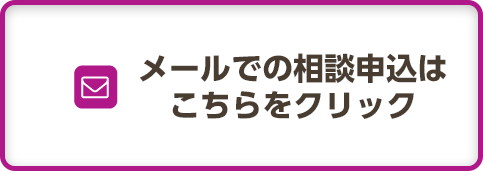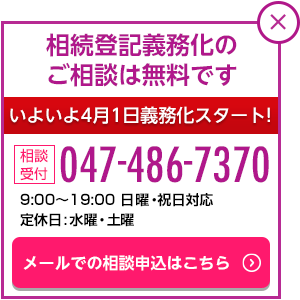【法務局とは】不動産名義変更/相続登記の手続き先どこでする?司法書士の役割とは
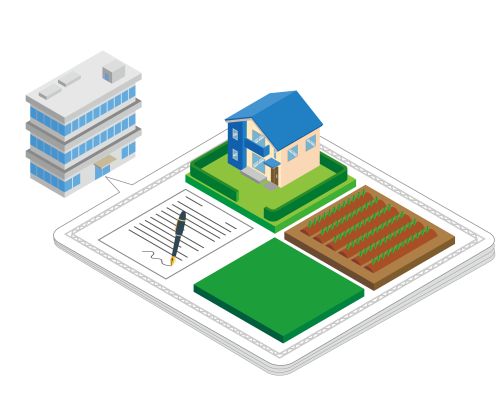
被相続人の相続財産の中に「不動産」が含まれている場合、相続時には新たに不動産を引き継ぐ際に「相続登記」を行う必要があります。相続登記とは不動産を被相続人名から、相続する方へと名義変更をする手続きです。では、相続登記をする際にはどこで手続きすればよいのでしょうか。
そこで、本記事では相続登記について、手続き先である法務局や手続きをサポートする司法書士の役割を中心に詳しく解説します。
相続登記(不動産の名義変更)をする場合はどこで手続きする?
相続によって不動産を取得し、相続登記が必要となった場合は「法務局」で手続きをします。
法務局は全国に8カ所、地方法務局は全国に42カ所が設置されており、さらに支局や出張所などを合わせると約400カ所が運営されています。この章では相続登記の手続き先である法務局について、相続登記の概要にも触れながら詳しく解説します
相続登記の概要
相続登記は不動産の所有者が亡くなった場合に、相続人への名義変更を行う手続きのことです。相続、だけではなく遺贈で不動産を受け取った方も相続登記をする必要があります。令和6年4月1日に以下のとおり義務化されており、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が科せられるおそれがあります。手続きには漏れがないように注意しましょう。
・相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
・遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりませ
法務局とは|相続登記を行える専門機関
相続登記は法務局に申請し、手続きを進めます。法務局とは法務省が管轄する専門機関で、不動産や法人の登記、登記簿謄本の発行などを担っています。法務局は全国に多数設置されていますが、どこでも自由に相続登記を申請できるわけではありません。不動産の登記については、「不動産の所在地」を管轄する法務局にて申請を行う必要があります。
たとえば、被相続人が千葉県内だけではなく、神奈川県内や茨城県内にも不動産を所有していた場合、それぞれの不動産を管轄している法務局へ登記申請を行います。多数の不動産を各地にお持ちの場合は、手続きに時間を要する可能性があるため、早期に準備を整えるようにしましょう。
参考URL
全国の法務局 ※https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
千葉県の法務局 ※https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/shikyokutou/all.html
相続登記に必要な書類と申請の流れ
相続登記を申請する場合には、必要書類を揃えた上で法務局へ申請を行う必要があります。この章では必要書類の一覧票を中心に、申請の流れを簡潔に解説します。
相続登記時|必要書類一覧票
どのように不動産を取得するかによって必要書類も異なるため、以下をご確認ください
| 法定相続どおり | 遺産分割による取得 | 遺贈による取得 | |
|---|---|---|---|
| 被相続人の戸籍謄本 | 出生~死亡まで | 出生~死亡まで | 死亡時の戸籍謄本のみで可能な場合あり |
| 亡くなった被相続人の住民票の除票 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 相続人の戸籍謄本 | 〇 | 〇 | 不動産を取得する方のみ必要 |
| 相続人の住民票 | 〇 | 不動産を取得する方のみ必要 | 不動案を取得する方のみ必要 |
| 相続人の印鑑証明書 | × | 〇 | × |
| 固定資産税評価証明書(コピー可) | 〇 | 〇 | 〇 |
※遺産分割協議を行った場合は、遺産分割協議書が必要
※遺贈によって取得する場合は、遺言書が必要
この他に、法務局の求めによって必要書類が追加される場合があります。
相続登記申請の流れとは?自分でもできる?
相続登記を行う場合、申請は以下の流れに沿って進みます。相続登記はご自身で行うことも可能です。
1. 必要書類を整える
遺言書がなかったり、法定相続分どおりに相続をしない場合はまず遺産分割協議を行います。遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作った上で相続登記の準備に入ります。
2. 法務局の窓口、もしくは郵便・オンラインで申請する
相続登記の申請は、法務局の窓口で行いますが遠方にある不動産を登記申請する場合には郵送での手続きも可能です。
窓口・郵送による申請時には「登記申請書」を添付します。以下リンクの「2 所有権の移転 2-1 相続」から、該当する不動産の取得方法に合わせてダウンロードしてご利用ください。
参考URL 法務局 不動産登記の申請書様式について
3. 登記完了
書類などに不備がなければ、申請からおおよそ10日間程度を目安に相続登記が完了します。完了後は窓口で本人確認書(運転免許証など)と申請時に使用した印鑑を持参すると、登記識別情報(別名:権利証)と登記完了証が受領できます。
自分で相続登記を申請する際の注意点
自分で相続登記を申請する際には、以下の注意点をあらかじめ押さえておくことがおすすめです。
1. 提出書類の原本には返却してもらえるものがある(原本還付)
相続登記時に使用した申請書類には、審査完了後に返却してもらえるものがあります。あらかじめ返して欲しい書類はコピーもセットで添付して提出しておく方法です。この方法を原本還付と呼びます。戸籍謄本や住民票などが返却してもらえ、別の相続手続きに使えますので、必要に応じてコピーを添えて提出しましょう。
2. 補正が発生することがある
法務局に相続登記を申請した結果、書類に不備があったり、追加書類が必要となった場合には「補正」が求められることがあります。補正とは、不備を訂正する手続きのことです。この時、持参による申請と郵送申請時には現地の法務局へ出向いて補正をする必要があります。
オンライン申請時にはオンライン上で補正が可能です。遠方の法務局へ郵送申請する場合は、補正のリスクを下げるためにも、あらかじめお近くの法務局に相談し書類を確認してもらうことがおすすめです。
相続登記における司法書士の役割とは?依頼するメリットを解説
登記手続きの専門家である「司法書士」は、相続登記を進める上でどのような役割を果たしているのでしょうか。この章では司法書士の役割や、相続登記を依頼するメリットをわかりやすく解説します。
相続登記における司法書士の役割
司法書士は相続登記の依頼を受けると、登記申請の準備から申請まで、ご依頼者様に代わって進めることができます。相続登記は被相続人が所有していた不動産を確認し、必要書類を漏れなく整える必要があり、不慣れな方が手続きを進めようとすると法務局から補正の指摘を受けやすくなります。
相続における手続きは登記だけではないため、多忙なその他の相続手続きの合間を縫って、何度も法務局へ足を運ばなければいけないおそれがあります。
そこで、登記の専門家である司法書士へのご依頼がおすすめです。司法書士へは相続登記だけではなく、遺産分割協議書の作成などもまとめて依頼できます。
■司法書士へ依頼できる相続登記以外の相続手続き
- 預貯金の名義変更
- 株式の名義変更
- 遺産分割協議書の作成 など
司法書士に相続登記を依頼するメリット
司法書士は相続手続き全般に精通しており、必要に応じて税理士などの専門家を紹介することも可能です。「どのように相続全般を進めたらいいのかわからない」と思ったら、まずは司法書士に相談してみましょう。
たとえば、遺産分割協議の段階で相続人の中に認知症などの症状で判断能力が低下している方がおられると、遺産分割協議を進めることができません。このようなケースでは判断能力が低下している相続人に、成年後見人が必要となる可能性が高いでしょう。司法書士は成年後見人の申立ても可能であり、遺産分割を円滑に進めるためのサポートができます。
相続人だけでは進めにくいような相続も、司法書士に依頼すると安全に進めていくことができます。
まとめ
今回の記事では、相続登記の申請先である法務局について、相続登記の概要にも触れながら詳しく解説を行いました。相続登記は義務化されており、定められた期限内に手続きを進める必要があります。ご自身でも申請できますが、多くの必要書類を整える必要があるため注意が必要です。
はながすみ司法書士事務所は相続の累計問合せ件数4,479件(2023年末まで)に上っている、経験豊富な司法書士事務所です。
千葉県の八千代市・佐倉市を中心に、相続登記や相続手続き全般の悩みについて丁寧に対応しています。相続登記義務化のご相談については無料で対応していますので、まずはお気軽にご連絡ください。