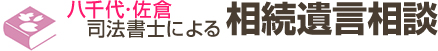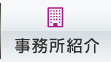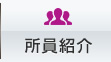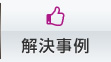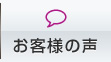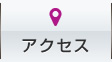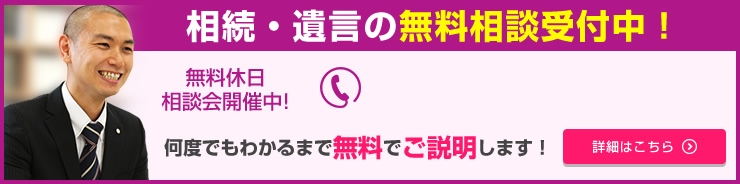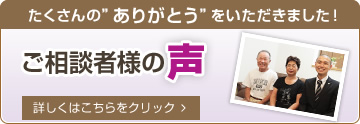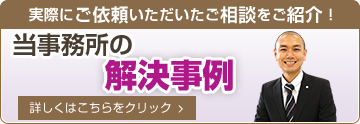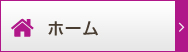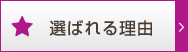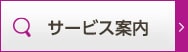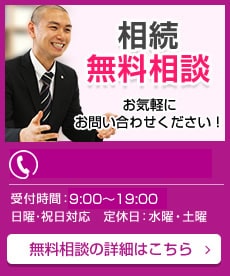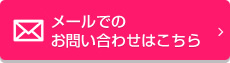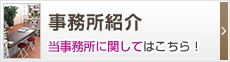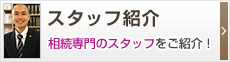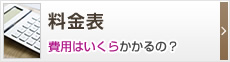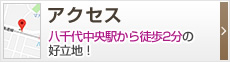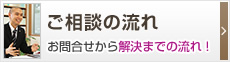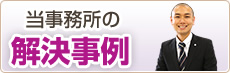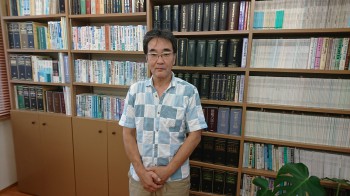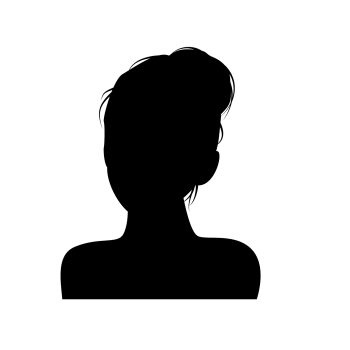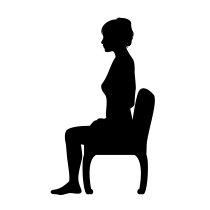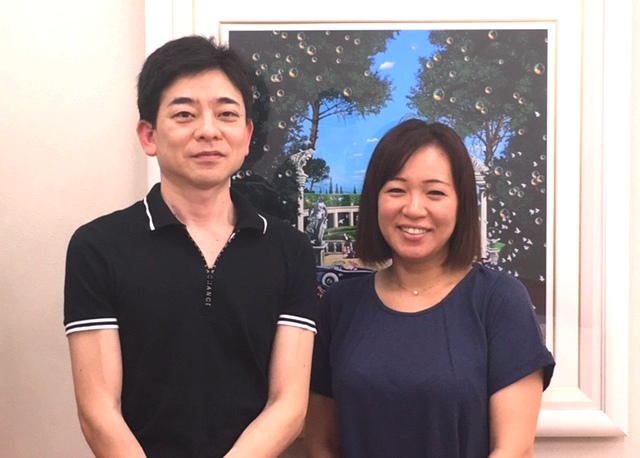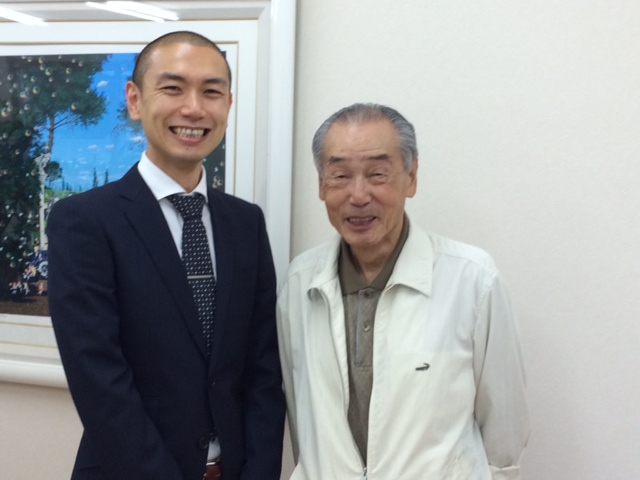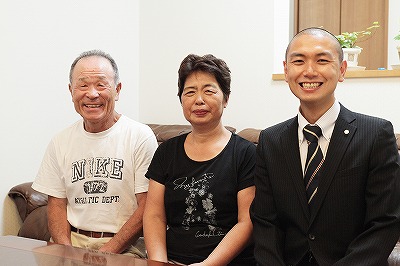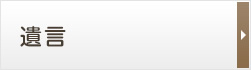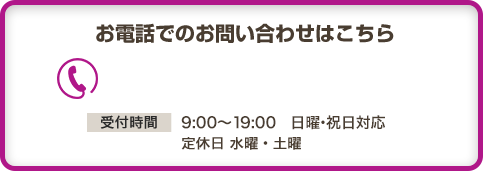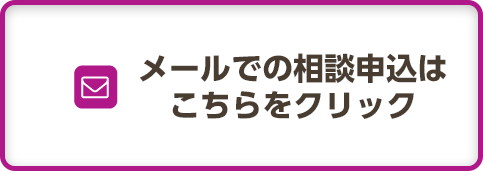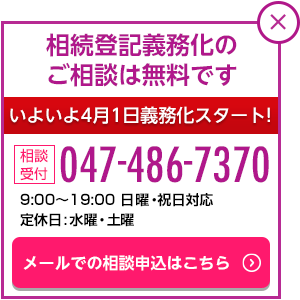親より先に子どもが死亡した場合の相続について解説!

子どもが親よりも先に亡くなると、遺産を相続する人はその子どもの家族構成によって変わります。たとえば、亡くなった子どもに配偶者や子どもがいれば、親ではなくその配偶者や子どもが相続人となります。
一方で、亡くなった子どもに配偶者や子どもがいない場合は、親が遺産を相続します。このとき、両親がともに健在であれば2人で遺産を分け、片方の親だけが存命ならその方がすべてを相続します。
本記事では、子どもが親よりも先に亡くなった場合の相続について、ケースごとに詳しく解説します。
相続は親の死亡時だけではない、子どもが先に死亡した時にも発生する
相続は親が亡くなったときだけ起こるものではありません。子どもが親より先に亡くなった場合にも相続が発生します。
そもそも相続が発生するためには、次の条件が必要です。
1. 被相続人が亡くなること
人が死亡すると、その瞬間に相続が発生します。死亡の事実が戸籍などで確認されることが重要です。
2. 相続財産が存在すること
相続の対象となる財産には、不動産や預貯金だけでなく、借金や保証人の責任なども含まれます。財産にはプラスとマイナスの両方があるため、注意が必要です。
3. 相続人がいること
相続人は法律で決まっています。配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などが相続人となる可能性があります。相続人がいない場合、財産は国に帰属します。
これらの要件が満たされれば、親が亡くなった場合でも、子どもが先に亡くなった場合でも同様に相続が発生します。
つまり、相続は「誰が亡くなったか」に関係なく、法律で定められたルールに基づいて発生します。このため、子どもが親より先に亡くなった場合も、相続の手続きが必要になることを覚えておきましょう。
自分より先に子どもが死亡した場合の相続で考えられる法定相続人の範囲
子どもが親よりも先に亡くなった場合、遺産を相続する人(法定相続人)は民法によって決められています。相続のルールは、亡くなった人(被相続人)の家族構成によって変わります。以下に、法定相続人の範囲を分かりやすく説明します。
配偶者は常に相続人
被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。配偶者は、他の相続人(子どもや親、兄弟姉妹)の順位に関係なく、常に相続権を持ちます。
子どもがいる場合
被相続人に子どもがいる場合、子どもが第一順位の相続人となります。配偶者がいる場合には、配偶者と子どもで財産を分け合います。この場合、親や兄弟姉妹に相続権はありません。
子どもがいない場合は親が相続人
被相続人に子どもがいない場合、親が第二順位の相続人となります。配偶者がいる場合は、配偶者と親が遺産を分け合います。もし配偶者がいない場合、親がすべてを相続します。
子どもも親もいない場合
被相続人に子どもも親もいない場合は、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。
配偶者がいれば、配偶者と兄弟姉妹で財産を分け合います。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(甥や姪)が代わりに相続人になります。
順位のルール
相続には順位があり、先順位の相続人がいる場合、後順位の相続人に相続権は発生しません。
ただし、先順位の相続人全員が相続を放棄した場合、後順位の相続人に相続権が移ります。
自分に子どもがなく親が離婚している場合、自分を育ててくれた親にだけ財産を残せる?
遺言書を作らずに亡くなると、自分の財産は法律に従って、自動的に両方の親に分けられます。親が離婚している場合でも、このルールは変わりません。
育ててくれた親にだけ財産を渡したい場合は、遺言書を作って対策をする必要があります。
遺言書での対策
両親のどちらかにだけ財産を残したい場合は、遺言書を作成することが重要です。
遺言書で「全財産を育ててくれた親に渡す」と明記すれば、自分の死後に意志を尊重してもらえます。
ただし、遺言書を作成しても、すべての財産を特定の相続人に渡すことが必ずしも保証されるわけではありません。その理由は「遺留分」という制度にあります。
遺留分とは?
遺留分とは、法定相続人に保証された最低限の取り分のことです。たとえば、親が相続人の場合、遺産全体の1/3が遺留分として確保されます。親が2人いる場合、それぞれ1/6ずつの権利を持ちます。
この遺留分は、遺言書があっても請求することが可能であり、放棄させるには家庭裁判所での手続きが必要であり、本人の同意がなければ実現しません。
片方の親にだけ財産を残す方法
遺留分の問題を避け、育ててくれた親にできるだけ多くの財産を残すためには、以下の方法を検討しましょう。
1. 遺言書に理由を明記する
遺言書に「なぜ育ててくれた親に全財産を渡したいのか」を具体的に書きましょう。親権を持たなかった親に対して、納得してもらえる理由を示すことが重要です。
ただし、相手が遺留分を請求しないと約束する保証はないため、絶対的な解決策ではありません。
2. 生前贈与の活用
遺産として残すのではなく、生きているうちに育ててくれた親に財産を贈与する方法もあります。
ただ、贈与税がかかる可能性があるため、税金対策を考慮する必要があります。
3. 専門家に相談する
相続や遺留分、生前贈与などの問題は専門家の知識が必要です。弁護士や司法書士に相談することで、最適な方法を提案してもらい、トラブルを未然に防ぐことができます。
息子や娘の配偶者に遺産を独り占めされないために
息子や娘の遺産が配偶者にすべて渡ってしまうことを防ぐには、事前の準備や遺言書の確認、法定相続分を考慮した適切な対応が求められます。
遺言書に「配偶者に全部相続させる」と書いてあった場合
まずは、遺言書に「配偶者に遺産を全部相続させる」と指定されているケースです。このような指定は、配偶者の生活を優先する意図からよく見られます。
この場合、最初に遺言書が有効かどうかを確認することが重要です。自筆証書遺言の場合、要式を満たさないことで無効となるケースがあります。また、遺言書が偽造や変造されている可能性がある場合もあるため、慎重に確認しましょう。もし遺言書が無効であれば、遺言書の内容にかかわらず法定相続分に基づいて分割されます。
一方、遺言書が有効であった場合には、指定どおりに配偶者が全ての遺産を相続します。ただし、この場合でも親は遺留分を請求する権利があります。相続人が親の場合、その遺留分は遺産全体の1/6(両親それぞれが健在の場合、遺留分割合は1/12)となります。
遺留分を請求するには、相続開始後および不公平な遺言を知った日から1年以内に手続きを行う必要があります。確実に権利を行使するためには、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行いましょう。
配偶者が遺産分割協議に応じない場合
遺言書がない場合でも、配偶者が遺産を抱え込み、親と遺産分割協議に応じないケースがあります。
このような場合は、遺産分割には「法定相続分」という目安があることを伝え、協議を進めるよう努めましょう。相続人が配偶者と親である場合、法定相続分は配偶者が2/3、親が1/3となります。
配偶者が「自宅を守りたい」「住み続けたい」などの理由で不動産を分けることを拒否する場合は、代償金の支払いを提案してみてください。代償金とは、不動産を取得する代わりに、他の相続人に金銭で補填する方法です。
それでも合意が難しい場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。調停では調停委員が間に入り、公平な分割を目指して話し合いを進めてくれます。調停でも合意に至らない場合は最終的に審判へ進み、裁判官が法定相続分に基づいて遺産の分割を決定します。これにより、一人が遺産を独り占めすることは認められません。
まとめ
親より先に子どもが亡くなった場合の相続は、通常の相続よりも慎重な対応が求められる場面が多くあります。配偶者が遺産を独占するリスクや、親族間でのトラブルを防ぐためには、早めの対策が欠かせません。
たとえば、遺言書の作成や確認、遺留分の請求、生前贈与の検討など、できる限り早い段階で準備を進めることで、不必要な争いを避けることができます。また、遺産分割協議がまとまらない場合には、法的手続きを検討することも選択肢の一つです。
相続手続きは、一見シンプルに思えても、法律や手続きの理解が必要な場面が多く、個人で対応するのは負担が大きい場合があります。こうしたときには、司法書士などの専門家に相談することで、効率的かつ円滑に手続きを進められるでしょう。
相続でお悩みの方は、一人で抱え込まず、ぜひ司法書士にご相談ください。専門家の力を借りることで、大切な財産やご家族の関係を守るための最善策が見つかるはずです。