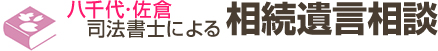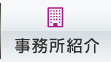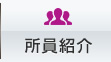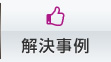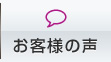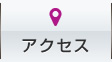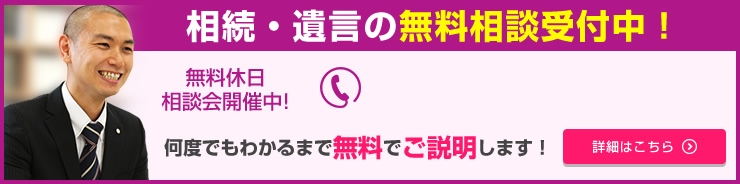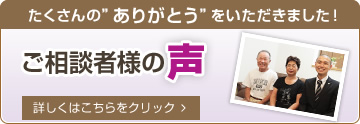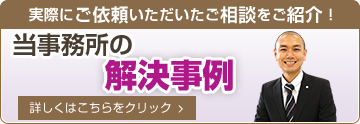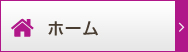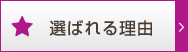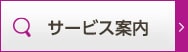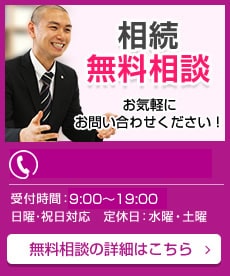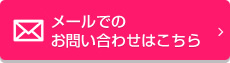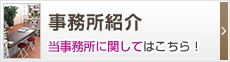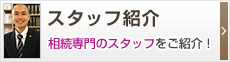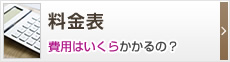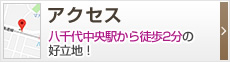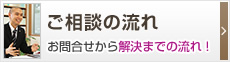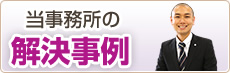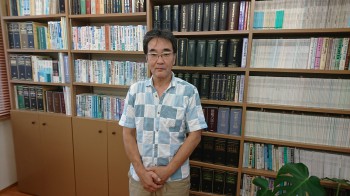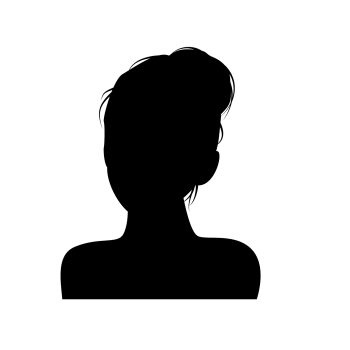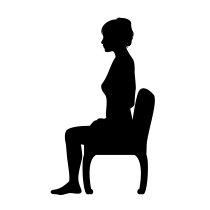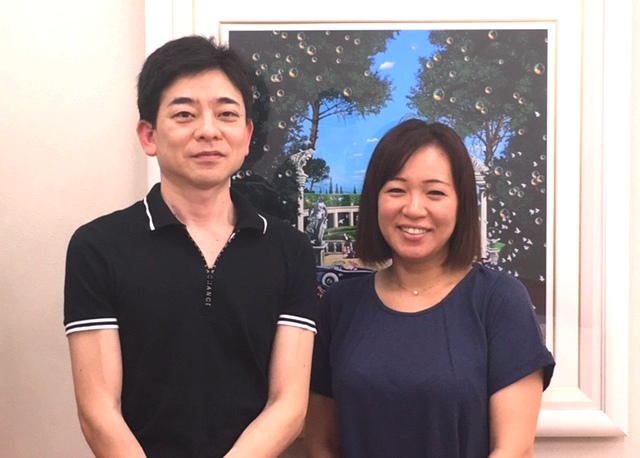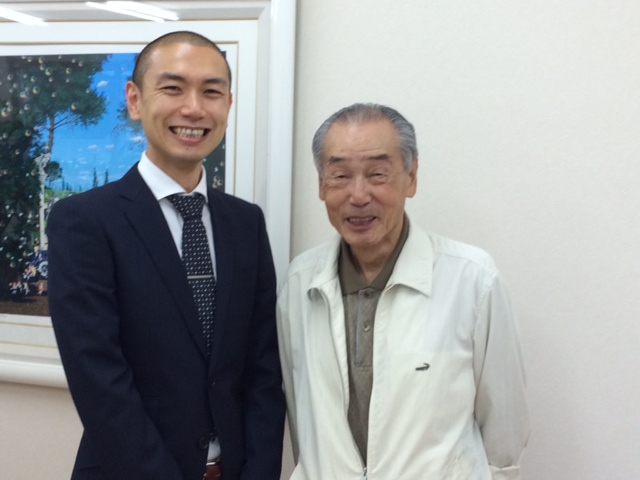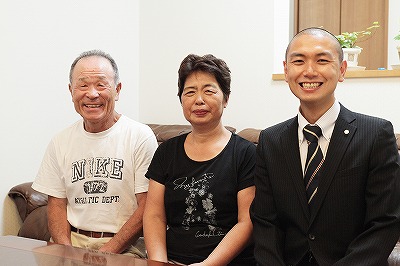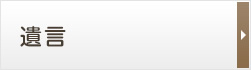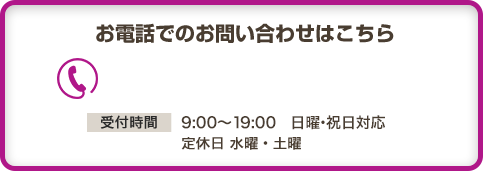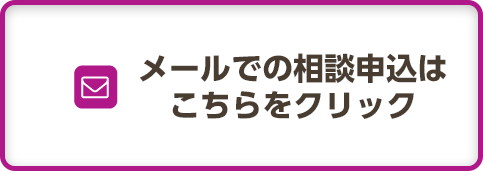【婿養子の相続】養親(妻の両親)・実親両方の相続権があるのか?

婿養子になったら、実の親と養親の両方の財産を相続できるのでしょうか?自分が婿養子の場合や、身内に婿養子がいる場合、この疑問を抱く人も多いはずです。
また、「婿養子」と「婿」は同じ意味ではありません。実は、多くの人がこの違いを誤解しています。本記事では、婿養子の相続権について詳しく解説し、婿との違いもわかりやすく説明します。
それでは、婿養子の相続権について見ていきましょう。
婿養子とは
「婿養子」とは、妻の親と養子縁組をした男性のことです。
結婚すると、一般的には夫の姓を名乗ることが多いですが、婿養子の場合は妻の姓を継ぎます。これは、妻の親と法律上の親子関係を結ぶためです。養親(妻の親)から見れば、法的に新たな子どもが増えることになります。
婿養子と混同されやすいものに「婿」というものがあります。どちらも妻の姓を名乗ることはできますが、決定的な違いは養子縁組をしているかどうかです。
- 婿養子:妻の親と養子縁組を結び、法的に親子関係が成立する
- 婿(婿入り):養子縁組をせず、単に結婚に伴い妻の姓を名乗る
婿養子になると、妻の親の法定相続人となり、遺産を相続する権利が生じます。一方で、養子縁組をしない「婿」は、法律上は妻の親とは赤の他人のままです。そのため、相続の権利はありません。
実子と婿養子の違い
実子と婿養子は、どちらも法律上の親子関係を持ちますが、その成り立ちや関係性には大きな違いがあります。
実子は血縁関係をもとに自然に親子関係が成立するのに対し、婿養子は養子縁組という法的手続きを経て親子関係を結ぶことになります。この違いにより、戸籍・扶養義務・姓の変更・親族関係などにも影響が出ます。
ここでは、実子と婿養子の違いについて詳しく説明します。
実子と婿養子の基本的な違い
実子とは、親から生まれた血縁関係のある子どものことを指します。出生と同時に親子関係が成立し、法律上の手続きなしに親の子として扱われます。
一方、婿養子とは、もともと別の家に生まれた男性が、結婚を機に妻の親と養子縁組を結ぶことで、法的な親子関係を持つようになった人を指します。養親との血のつながりはありませんが、法律上は実子と同じ扱いになります。
戸籍の違い
実子は、生まれたときから親の戸籍に入ります。親が本籍を移動しない限り、基本的に同じ戸籍のままです。結婚すると配偶者と新しい戸籍を作りますが、実親との親子関係はそのまま維持されます。
一方、婿養子は、養子縁組をすると養親の戸籍に入るのが一般的です。また、養子縁組を解消すれば元の戸籍に戻ることも可能ですが、そのためには手続きが必要になります。
姓(名字)の違い
実子は、基本的に親と同じ姓を名乗ります。結婚すると、夫婦のどちらかの姓を選び、新しい戸籍を作りますが、姓を変えないことも可能です。
婿養子になると、多くの場合妻の姓を名乗ることになります。これは、養子縁組を結ぶことで、養親の子として扱われるためです。ただし、必ずしも姓を変える必要はなく、婚姻時に夫婦のどちらの姓を選ぶかで決まります。
扶養義務の違い
実子は、親が高齢になったり、生活が困難になったりした場合、実親を扶養する義務を負います。これは血縁に基づく義務であり、生涯続きます。
婿養子は、実親に加えて、養親に対しても扶養義務を持ちます。たとえば、養親と実親の両方が介護を必要とする場合、その費用負担や手続きが重くなることも考えられます。扶養義務が二重になる点は、婿養子ならではの負担といえるでしょう。
親子関係の解消の違い
実子の場合、親子関係は一生続きます。たとえ絶縁状態になったとしても、法律上は親と子であり続け、親の扶養義務や相続権は消滅しません。たとえば、親と何年も連絡を取っていなくても、法律上は親の介護や生活の扶助を求められる可能性がありますし、親が亡くなれば相続権が発生します。
親子関係を完全に断ち切るためには、特別養子縁組の成立や戸籍上の手続きを経る必要があります。しかし、これらの手続きには厳格な条件があり、一般的に実子が親との関係を一方的に解消することは極めて困難です。
一方、婿養子の場合、養親と養子の合意があれば養子縁組を解消できます。養子縁組を解消すると、養親との相続権や扶養義務もなくなり、戸籍も元に戻すことができます。
婿養子の相続のメリット・デメリット
婿養子になることで、相続の面で一般的な結婚とは異なる扱いを受けます。メリットも多い一方で、注意すべきデメリットもあります。ここでは、婿養子の相続について詳しく解説します。
婿養子の相続におけるメリット
婿養子の相続には、次のようなメリットがあります。
1. 養親と実親、両方の財産を相続できる
婿養子は、養親(妻の親)と実親の両方の相続権を持つという大きなメリットがあります。養子縁組を結ぶことで、養親の法定相続人となります。そのため、養親が亡くなった際には、実の子どもと同じように遺産を受け取ることができます。
さらに、養子になったとしても実親との親子関係は維持されるため、実親の遺産も相続可能です。つまり、一般的な結婚では得られない、二つの家からの相続が可能になるという特徴があります。
2. 実子と同じ割合で相続できる
婿養子は、養親の実子と同じ相続割合を持ちます。たとえば、妻の親が亡くなり、相続人が「妻」「妻の兄」「婿養子」の3人だった場合、法定相続分はそれぞれ3分の1ずつになります。
「養子だから相続分が少ない」ということはなく、法律上、実子と平等な扱いを受けます。
3. 代襲相続や遺留分請求も可能
婿養子にも、代襲相続や遺留分侵害額請求の権利があります。
代襲相続とは、本来の相続人が亡くなっている場合に、その子どもや孫が代わりに相続する制度です。たとえば、妻の祖父が亡くなった際に、妻の父がすでに他界している場合、婿養子も祖父の遺産を相続できる可能性があります。
遺留分とは、法定相続人が最低限確保できる相続分のことです。もし養親が遺言書で「婿養子には一切遺産を与えない」と記していても、法定相続分の2分の1を遺留分として請求できます。
婿養子の相続におけるデメリット
婿養子の相続には、次のようなデメリットがあります。
1. 離婚しても養子関係は続く
婿養子になった場合、妻と離婚しても養親との親子関係は自動的には解消されません。婚姻関係と養子縁組は別の手続きであり、養親と養子の双方の合意がなければ養子縁組は解除できないのです。
また、妻が亡くなった場合も、特に手続きをしなければ養親との親子関係は継続します。養親との関係を解消したい場合は、正式な手続きを踏むことが必要です。
2. 借金などの負債も相続するリスク
相続は、必ずしもプラスの財産ばかりではありません。亡くなった人が借金を抱えていた場合、その借金も相続することになります。
婿養子は養親・実親の両方から相続するため、それぞれの負債を背負うリスクがあります。こうしたケースでは、相続を放棄することも検討しなければなりません。相続放棄をすることで、負債を引き継がずに済みます。ただし、一度相続放棄をするとプラスの財産も受け取れなくなるため、慎重に判断する必要があります。
3. 実子との相続トラブルが起こりやすい
婿養子になると、養親の実子(妻の兄弟姉妹)と遺産分割をめぐってトラブルになることがあります。
婿養子の分だけ相続人の数が増え、1人あたりの相続額が減るためです。特に、遺産の多くが不動産の場合、売却しなければ分割できないこともあり、さらに争いが激しくなることがあります。こうした問題を避けるためには、あらかじめ養親・妻の兄弟姉妹としっかり話し合いをしておくことが重要です。
婿養子の相続における相続税
婿養子として相続する場合、気になるのが相続税の扱いです。実子と同じように相続できるとはいえ、相続税の計算には婿養子ならではのポイントがあります。ここでは、基礎控除額への影響と2割加算の適用有無について、わかりやすく解説します。
婿養子は基礎控除額を増やせる
相続税は、相続財産から基礎控除額を差し引いた課税遺産総額に対して課税されます。基礎控除額は、次の計算式で求められます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
この法定相続人の数には婿養子も含まれるため、養子縁組をしていると控除額が増え、相続税の負担が軽減される可能性があります。
また、生命保険の死亡保険金や、会社から支給される死亡退職金にも非課税枠があります。これらの非課税限度額は以下のように決まります。
500万円×法定相続人の数
つまり、法定相続人が多いほど非課税枠も広がるため、婿養子は節税面で有利になることがあります。
ただし、養子が法定相続人として認められる数には以下のとおり上限があります。
| 被相続人に実子がいる場合 | 被相続人に実子がいない場合 |
|---|---|
| 養子は1人まで法定相続人に含まれる | 養子は2人まで法定相続人に含まれる |
たとえば、養親に実子がいる状態で養子縁組をしても、2人以上の養子は基礎控除額の計算に含めることができません。この点は、節税対策として養子縁組を考える際には注意が必要です。
婿養子は2割加算の対象にならない
相続税には「2割加算」という仕組みがあります。これは、被相続人(亡くなった人)の配偶者や一親等以外の人が相続すると、相続税が2割増しになる制度です。
2割加算の対象となるのは、次のような関係の人たちです。
- 被相続人の孫(世代飛ばしの相続を防ぐため)
- 被相続人の兄弟姉妹
- 被相続人の子の配偶者(例:妻の父から婿へ相続する場合)
婿養子は養親と養子縁組を結んでいるため、法律上「一親等の直系卑属(実子と同じ扱い)」になります。そのため、2割加算の対象外となり、相続税の負担が軽くなるのです。
まとめ
ここまで、婿養子の相続権や実子との違い、相続税の取り扱い、メリット・デメリットについて解説しました。婿養子になることで、養親と実親の両方の相続権を持つことができるという大きなメリットがあります。一方で、扶養義務の増加や、相続時のトラブル、負債を相続するリスクなどの注意点もあるため、事前にしっかりと理解しておくことが大切です。
ただし、相続に関するルールは非常に複雑であり、一般の方が正確に理解するのは難しいのが現実です。「自分の場合、婿養子としてどのような権利や義務があるのか?」「相続税の負担を軽減するためにはどのような手続きが必要か?」といった疑問をお持ちの方は、早めに専門家に相談することをおすすめします。