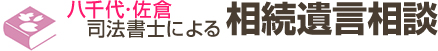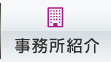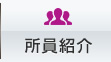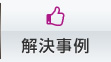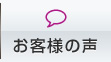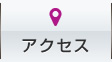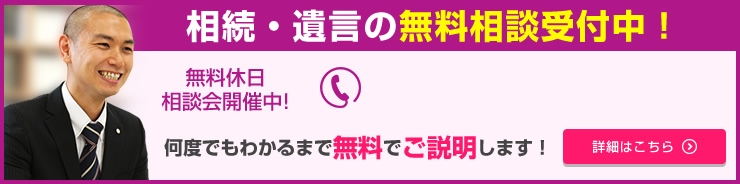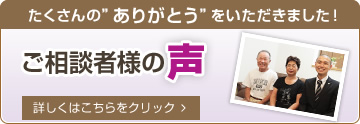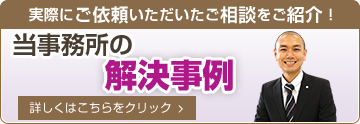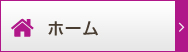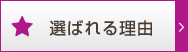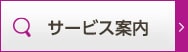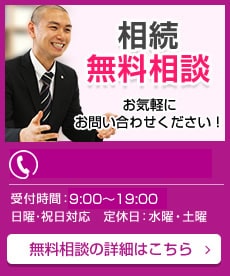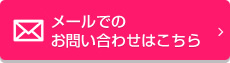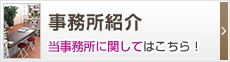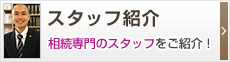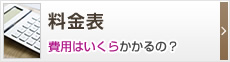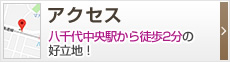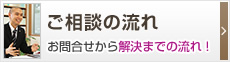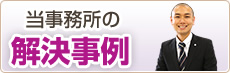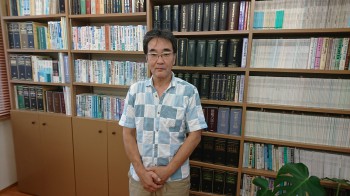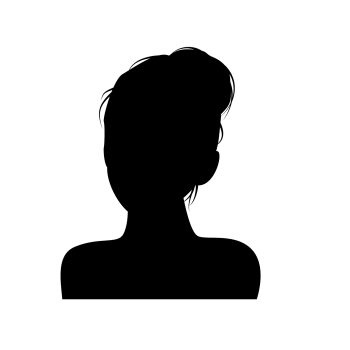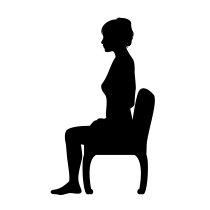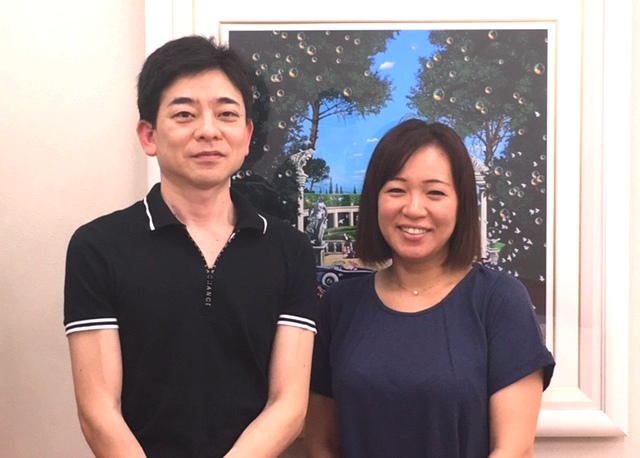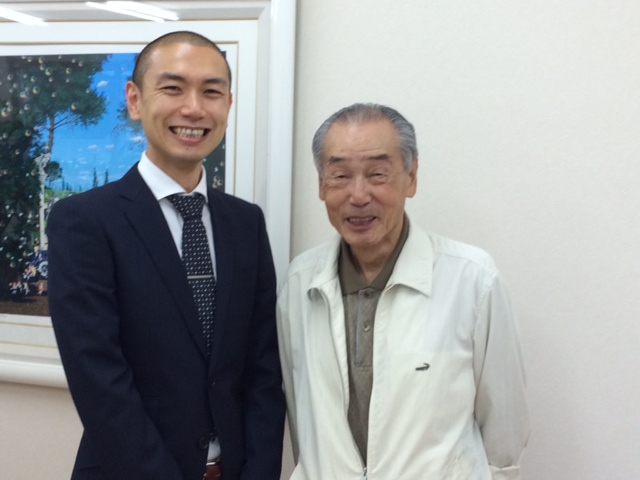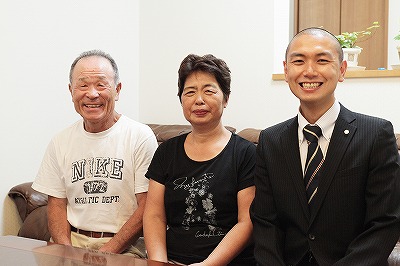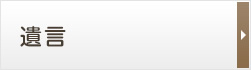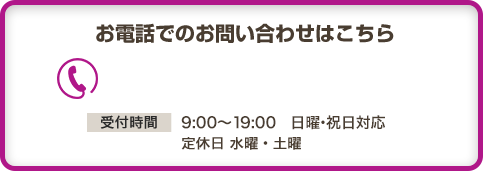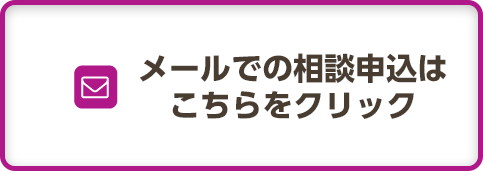【相続対策そこが知りたい】養子縁組をした方がいいのか・遺言書にするか?違いについて解説。

「自分の財産を、特定の人にきちんと遺したい」――そんなとき、選択肢としてよく出てくるのが「養子縁組」と「遺言書」です。たとえば、祖父が孫に財産を渡したいと考えた場合、どちらの方法がよいのでしょうか?
この記事では、それぞれの仕組みやメリット・デメリットをやさしく解説します。
相続対策での養子縁組のメリット・デメリット
養子縁組とは、血のつながりがなくても、法律上の「親子」として関係を作ることができる制度です。たとえば、祖父が孫を養子にすれば、孫は祖父の「子」として正式に相続人となります。
この制度は、相続対策のひとつとしてよく使われていますが、よい面と注意すべき点の両方があります。
養子縁組をするメリット
養子縁組をするメリットは主に以下の4つです。
① 相続税の節税につながる
相続税には「基礎控除」という非課税枠があります。この金額以内の財産なら、相続税はかかりません。基礎控除の金額は、法定相続人の人数によって決まります。
【基礎控除の計算式】
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
たとえば、相続人が2人いれば、基礎控除は4,200万円。養子を1人加えて相続人が3人になれば、控除額は4,800万円になります。
※ただし、養子を何人でも加えてよいわけではありません。税務上カウントできる養子の数には上限があります。
- 実の子がいる場合→養子1人まで
- 実の子がいない場合→養子2人まで
これを超えて養子にしても、相続税の計算では人数に含めてもらえません。
② 孫などの「本来相続人ではない人」にも遺せる
普通、孫は相続人ではありません。しかし、祖父が孫を養子にすると、孫は「子」として相続権を持てるようになります。
これにより、親を飛び越えて孫に直接財産を残すことができるのです。「自分の財産は孫に託したい」と考える高齢者の方にとって、大きなメリットです。
③ 遺言がなくても相続できる
養子になると「法定相続人」になるため、遺言書がなくても法律に基づいて財産を受け取れます。遺言書を作成し忘れた場合にも安心です。
④ 家族としてのつながりができる
法律上の親子になるため、たとえば介護や見守りなど、相手との関係を深めるきっかけにもなります。「ただのお世話してくれた人」ではなく、「自分の家族」として扱えるようになる点も見逃せません。
養子縁組をするデメリット
養子縁組をするデメリットは主に以下の4つです。
① 一度結んだら簡単にやめられない
養子縁組は、結婚と同じように正式な法律関係です。関係をやめる(=離縁する)には、養親と養子の両方が合意しないといけません。
もしどちらかが反対すれば、家庭裁判所に申し立てをして、手続きを進めなければならず、時間も手間もかかります。気まずくなったからといって、すぐに解消できるものではありません。
② 他の相続人との関係がこじれることも
「長男の子どもだけが祖父の養子になった」
「一部の親戚だけを相続人にした」
こうした養子縁組があると、他の相続人から「不公平だ!」と反発される可能性があります。
結果として、遺産分割の話し合いがこじれたり、家庭内の関係が悪くなったりすることもあるので注意が必要です。
③ 養子の苗字(名字)が変わる場合がある
基本的に、養子は養親の姓を名乗ります。たとえば、孫を祖父の養子にした場合、孫の苗字が祖父の苗字に変わることがあります。
学校生活や保険証・パスポートなど、生活への影響が出ることもあるため、事前に確認しておきましょう。
④ 孫を養子にした場合、相続税が高くなることも
孫を養子にすると、原則として相続税が2割増しになります。これは、「本来は相続人ではない人」が財産をもらったときに課されるペナルティのような制度です。
ただし、以下のようなケースでは2割加算の対象外になることがあります。
- 孫が代襲相続人(たとえば、親が亡くなっていて代わりに相続する)である
遺言によって遺贈する場合のメリット・デメリット
相続対策としてもうひとつよく使われる方法が、「遺言書」の作成です。遺言書とは、自分が亡くなったあと、どの財産を誰に渡すかを自分の意思で決めておく文書です。
たとえば、祖父が「自分のすべての財産を孫に渡したい」と考えたとき、遺言書を作れば、それが可能になります。孫が正式な相続人でなくても、「受遺者」として財産を受け取ることができます。
では、遺言による「遺贈」には、どんなメリットとデメリットがあるのでしょうか?
遺言によって遺贈するメリット
遺言によって遺贈するメリットは、主に以下の3つです。
① 誰にでも自由に財産を渡せる
遺言書の一番の強みは、「誰にでも財産を渡せること」です。養子縁組の場合は、法律上の親子関係が必要ですが、遺言なら親子でなくても問題ありません。
たとえば、長年お世話になった友人や介護をしてくれた人、応援している団体などに財産を渡すことができます。
② 内容をいつでも変更できる
一度作った遺言書は、あとから自由に書き直すことができます。気持ちが変わったり、状況が変わったりしたときにも対応しやすく、柔軟に使えるのが特徴です。
③ 遺言執行者を決めておける
遺言書の中で「遺言執行者」を指定しておけば、その人が代わりに手続きをしてくれます。相続手続きは意外と大変なので、家族の負担を減らすことができます。
遺言によって遺贈するデメリット
遺言はとても便利な手段ですが、注意点もあります。
① 遺留分を請求される可能性がある
遺言書で「すべての財産を孫に渡す」と書いても、ほかの相続人が納得しない場合があります。
たとえば、祖父には子ども(孫の親)や、祖父の兄弟姉妹など、法律上の相続人がいると、その人たちには「遺留分」という最低限の取り分を請求する権利があります。
孫がすべての財産を受け取った場合、父や叔母が「自分の遺留分をよこせ」と請求してきたら、それを拒否することはできません。
② 書き方を間違えると無効になることがある
とくに「自筆証書遺言」は、すべて自分の手で書く必要があります。日付がなかったり、署名がなかったりすると、その遺言は無効になることもあります。せっかく気持ちをこめて書いても、正しい形式でなければ使えなくなるおそれがあるのです。
不安な場合は、公正証書遺言(公証人が作成してくれる方式)を選ぶと安心です。
判断のポイント
相続対策を考えるとき、「養子縁組」と「遺言書」のどちらを選べばよいかは、財産の内容や、誰に渡したいのか、家族との関係性など、さまざまな要素をふまえて判断する必要があります。
ここでは、選ぶ際のポイントを、具体的なケースごとに紹介します。
養子縁組が向いている場合
養子縁組は、相続人を法律的に増やしたり、税金の負担を減らしたりするために活用される制度です。以下のようなケースに当てはまる方は、養子縁組を検討するとよいでしょう。
① 相続税の基礎控除を増やしたいとき
養子を増やすことで「法定相続人の数」が増えます。相続税の基礎控除額は、この人数によって決まるため、結果的に節税につながる可能性があります。
例:
法定相続人が2人の場合→基礎控除額は3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
養子を1人加えて3人にした場合→3,000万円+(600万円×3)=4,800万円
このように、控除額が大きくなることで、相続税の負担を軽くできることがあります。
② 孫に「子ども」として正式に相続させたいとき
孫は、もともとは法定相続人ではありません。しかし、養子縁組をすれば「子」として扱われ、他の子どもと同じように財産を受け取ることができます。
たとえば、「子どもと疎遠になっているので、孫に直接財産を残したい」と考える場合には、孫との養子縁組が効果的です。
③ 遺言を作らなくても相続できるようにしたいとき
養子にすると、相手は法定相続人になります。つまり、遺言書がなくても相続できる状態になります。
「万が一、遺言書を準備する時間がないまま亡くなってしまった場合でも、財産を確実に渡したい」という方にとっては安心です。
④ 単なる手続きではなく、「家族」としての関係を大切にしたいとき
養子縁組は、法律上の親子関係を結ぶ手続きです。単に財産を渡すだけでなく、「家族としてつながっていたい」という想いを形にすることもできます。精神的なつながりを大切にしたい方には、非常に意味のある制度といえるでしょう。
遺言が向いている場合
一方で、以下のような事情がある場合には、遺言をおすすめします。
① 誰に渡すかを自由に決めたいとき
遺言書があれば、親族だけでなく友人や介護してくれた人、支援したい団体など、どんな相手にも財産を渡すことができます。
養子縁組のような制限がないため、渡したい相手が相続人ではない場合でも、遺言書を使えば希望が実現できます。
② 将来的に考えが変わる可能性があるとき
遺言書は、一度作ったあとでも、何度でも書き直すことができます。たとえば、「状況が変わった」「渡したい相手との関係が変わった」といったときでも、新しい遺言書を書けば、以前の内容を簡単に取り消せます。
このように、柔軟に対応できる点は、養子縁組にはない大きなメリットです。
③ 法定相続人を増やしたくないとき
養子縁組をすると、相続人の数が増えます。すると、遺産分割協議に参加する人も増え、話し合いが複雑になる可能性があります。
その点、遺言書なら法定相続人の数は変わらず、手続きも比較的スムーズです。「家族の人数は増やさずに、自分の意思をきちんと伝えたい」という方には、遺言書のほうが適しています。
④ 財産の内容が複雑なとき
たとえば、不動産や株式などを持っていて、それを誰にどう渡すかを明確に決めておきたいときにも、遺言書は便利です。
さらに、遺言書で「遺言執行者」を指定しておけば、その人が相続の手続きを代わりに行ってくれるため、家族の負担を減らすこともできます。
司法書士に相談
相続対策は、家族構成や財産の内容によって最適な方法が変わるため、一人で判断するのは難しいこともあります。養子縁組にするか、遺言書にするかで悩んだときは、早めに専門家へ相談するのがおすすめです。
司法書士は、遺言書の作成サポート、不動産の名義変更など、相続に関する幅広い業務に対応しています。まずは自分の考えを整理するためにも、専門家に話してみることから始めてみましょう。
※関連記事はこちら