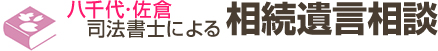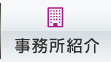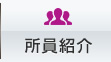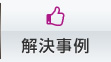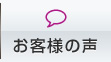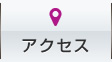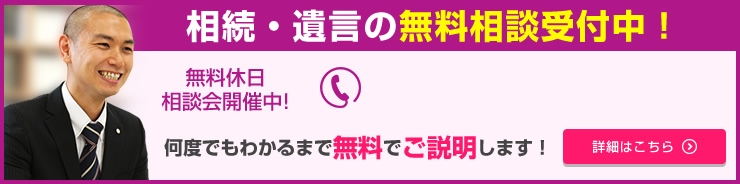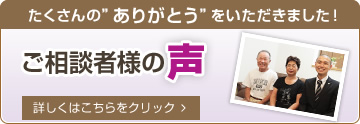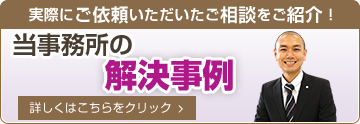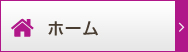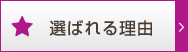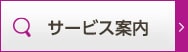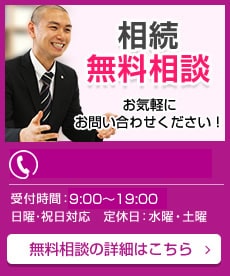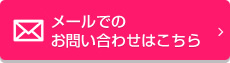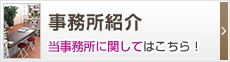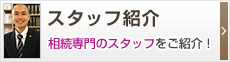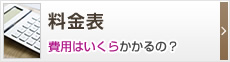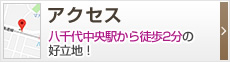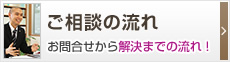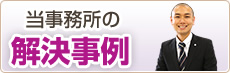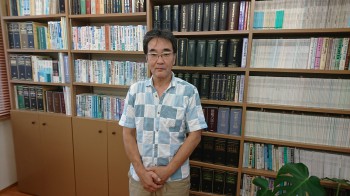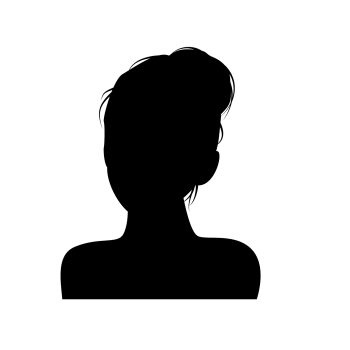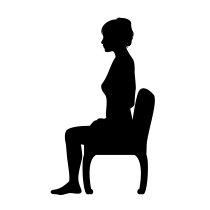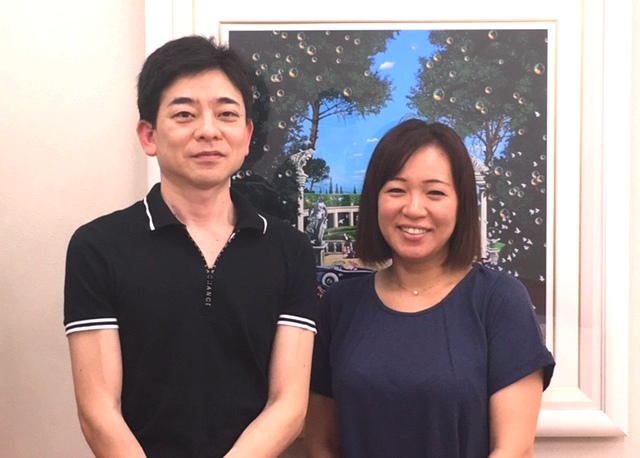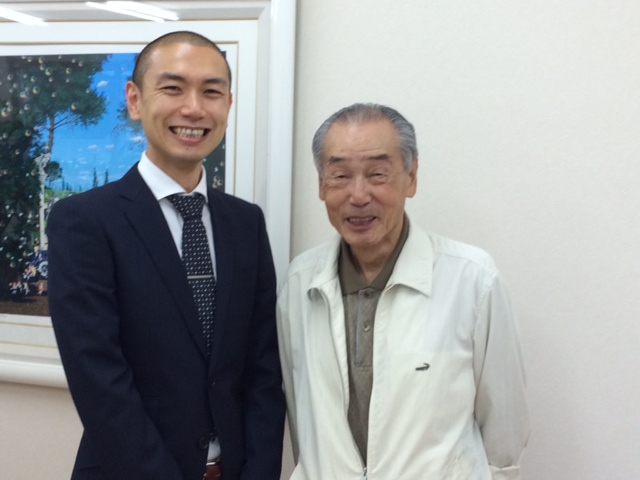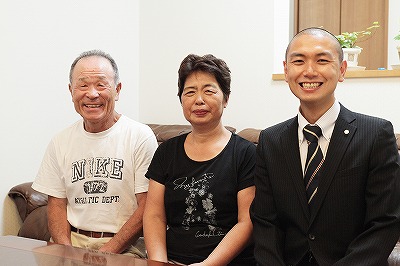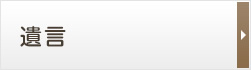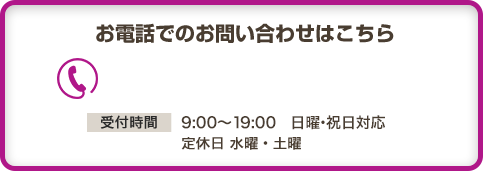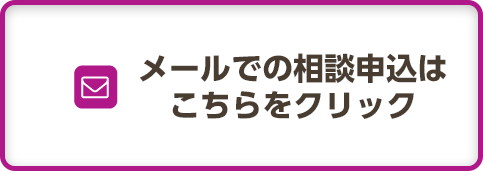【遺言書作成のタイミング】人生の節目に遺言書作成を考える

遺言書は、亡くなった後に家族が困らないようにするための、大切な準備です。
しかし、「いつ書けばいいのか」「どんなときに考えればいいのか」と迷う人も少なくありません。
実は、遺言書は年齢に関係なく、思い立ったときに作成できます。
人生の節目ごとに見直しておくことで、思いがきちんと届く遺言書になります。
この記事では、遺言書を作成するタイミングや、変更の可否、公正証書遺言の手続き、司法書士への相談について、わかりやすく解説します。
誰でも、どんな年齢でも遺言書の作成は可能か?
遺言書は、15歳以上であれば誰でも作成できます。これは民法961条で決められているルールです。15歳という年齢は、ふつうの契約ができる年齢(原則として18歳)よりも早くなっています。
なぜなら、遺言書は「自分が亡くなったあとのこと」を決める特別なものだからです。たとえ若くても、自分の財産をどう分けたいか、自分の思いを残すことは大切だと考えられています。
ただし、単に年齢だけでなく、「内容をしっかり理解できるかどうか」も重要です。これを法律では「遺言能力」と呼びます。
たとえば、認知症が進んでいたり、判断力が落ちている状態で書いた遺言は、あとで無効とされる可能性があります。遺言書を有効にするには、「自分の意思で、きちんと内容を理解して書いた」ことが必要です。
人生の節目に遺言書作成を考える
遺言書は、人生の大きな出来事のタイミングで考えるのが理想的です。生活環境や家族構成に変化があったとき、自分の想いをきちんと残しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。ここでは、遺言書を考えるきっかけになりやすい「人生の節目」と、それぞれの場面での注意点を紹介します。
結婚・出産のとき
結婚すると配偶者が法定相続人になります。出産すれば子どもも相続人に加わります。これにより、自分が亡くなったあとに財産をどう分けるか、考えておく必要が出てきます。
たとえば「家は配偶者にすべて残したい」「子どもには将来のために貯金を分けたい」など、希望があるなら遺言書に記しておきましょう。家族が増えるタイミングは、遺言書を作成または見直す良い機会です。
住宅を購入したとき
マイホームの購入も、遺言書を考える重要なタイミングです。家は大きな財産であり、相続のときに誰が受け取るかで争いが起こることもあります。
たとえば「妻が住み続けられるようにしたい」「長男に家を渡し、ほかの財産は他の子に分けたい」といった希望があるなら、遺言書で明確にしておくことが大切です。住宅ローンが残っている場合は、その扱いについても記しておくと安心です。
離婚したとき
離婚は、相続の対象となる人が変わる大きな転機です。離婚前に作った遺言書では、元配偶者が財産を受け取る内容になっているかもしれません。
こうした場合は、遺言書の内容をすぐに見直すべきです。
定年退職を迎えたとき
定年後は、これまでの仕事を終え、ゆとりある時間が持てる時期です。退職金などのまとまった財産をどう扱うか考えるよい機会でもあります。
このタイミングで、自分が持っている財産を誰にどのように渡したいかを整理し、遺言書にしておくと、家族も安心できます。体調の変化や老後の生活も見据えながら、じっくり準備ができる時期です。
配偶者と死別したとき
配偶者を亡くしたあとは、心身ともに大きな負担がかかります。同時に、生活の中心や財産の管理も変化することが多くあります。
このような時期に、自分の財産をどのように分けるかを見直すことは、次の世代への配慮にもなります。また、再婚の可能性がある場合など、今後の変化を見越して、遺言書に反映させることも大切です。
遺言書は何度でも・いつでも変更(書き変え)が可能なのか?
遺言書は、作成したあとでも、何度でも書き直すことができます。法律上、遺言者が生きている限り、いつでも自由に内容を変更できます。
たとえば、「この遺言書の内容は変えません」と相続人と約束したとしても、その約束は法的な効力を持ちません。本人の意思が変われば、何度でも書き直すことが認められています。
また、書き直しに回数の制限はありません。10回でも20回でも、必要があれば何度でも新しい遺言書を作成できます。
遺言書の内容は、人生の変化に応じて見直すのが自然です。いまの気持ちに合った内容に更新することで、残された家族への思いやりがより確かな形になります。
公正証書遺言は自筆証書遺言で変更することもできるがおすすめしない
変更は、公正証書遺言ではなく、自筆で書いた遺言書で行うこともできます。ただし、自筆証書遺言は、書き方に決まりが多く、少しでもルールから外れると無効になってしまうおそれがあります。
また、自宅で保管していると見つけてもらえなかったり、勝手に破棄されたりするリスクもあります。
近年は、法務局に保管してもらえる制度もありますが、それでもやはり、公正証書遺言として作り直すのが一番確実です。
公正証書遺言を変更する手順
公正証書遺言とは、公証人という法律の専門家に内容を伝え、公証役場で正式な書類として作ってもらう遺言書のことです。
自筆で書く遺言書とはちがい、法律のルールに沿って作られるため、内容が正確で、無効になるリスクが少ないのが特長です。さらに、公証役場が原本をしっかり保管してくれるので、なくしたり書きかえられたりする心配もありません。
公正証書遺言の内容を変更したい場合は、原則として、あらたに遺言書を作り直します。
前の遺言と新しい遺言に矛盾がある場合は、あとから作ったほうが優先されます。
変更の手続きの流れ
公正証書遺言の変更手続きの流れは、以下のとおりです。
①必要書類をそろえる
- 戸籍謄本
- 印鑑登録証明書
- 財産の内容がわかる資料(不動産、預貯金など)
- 証人になってもらう人2名の準備(家族などはなれないので注意)
②公証役場で新しい遺言書を作成する
公証人に相談しながら、あらたな遺言書を作ります。証人2人と一緒に署名・押印すれば完成です。
③作成した遺言書は公証役場で保管される
原本は公証役場で大切に保管されるため、なくしたり書きかえられたりする心配がありません。
司法書士に相談
遺言書を作ろうと思っても、どこから手をつけてよいかわからないという方は少なくありません。そんなときは、司法書士に相談するのも一つの方法です。司法書士は、相続や不動産登記などに詳しい法律の専門家で、遺言書の作成や見直しにも対応しています。
公正証書遺言を作成するには、公証人とのやりとりや必要書類の準備、証人の手配など、慣れていないと難しく感じる手続きがいくつもあります。司法書士に相談すれば、これらの作業をスムーズに進めるためのサポートを受けることができます。たとえば、財産の整理や相続人の確認、公証人との連絡、必要書類のチェックなど、ひとつひとつ丁寧に教えてもらえるため、不安を解消しながら進められます。
また、遺言書の内容について法的に問題がないかを確認してもらえるのも大きなメリットです。せっかく遺言書を作っても、内容に不備があると無効になる可能性があります。特に、相続人以外の人に財産を渡したい場合や、不動産の相続方法に悩んでいる場合など、慎重な検討が必要なケースでは、専門家のアドバイスが重要になります。
司法書士事務所の中には、初回相談を無料で行っているところもあります。費用面が気になる方も、まずは一度相談してみるとよいでしょう。遺言書を正しく、そして安心して残すためには、信頼できる司法書士のサポートを活用するのが賢明です。