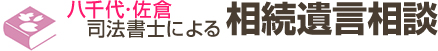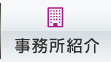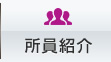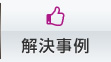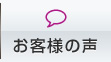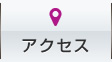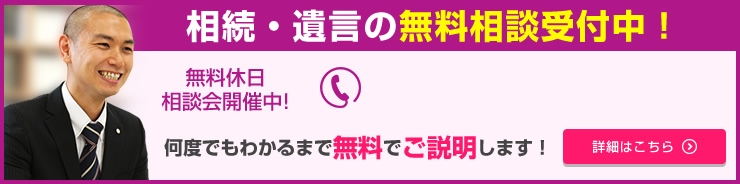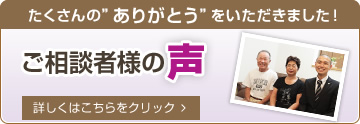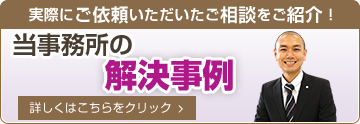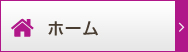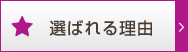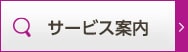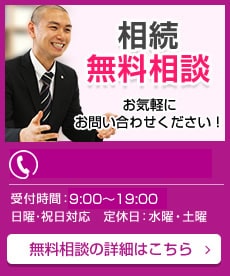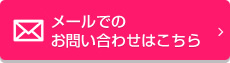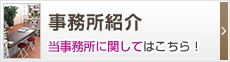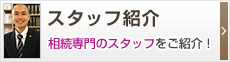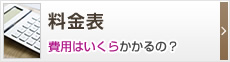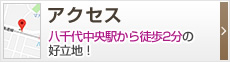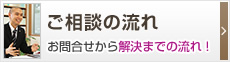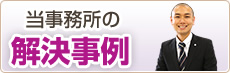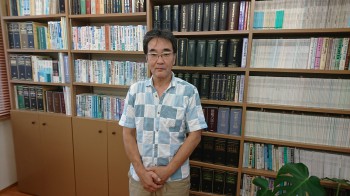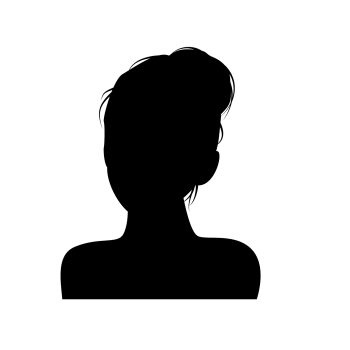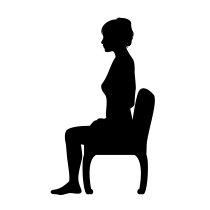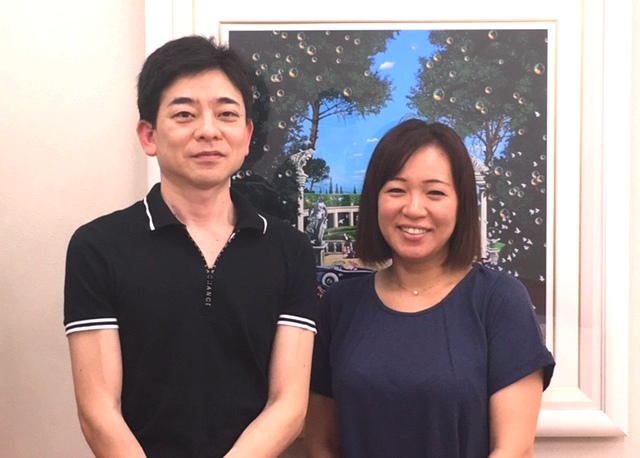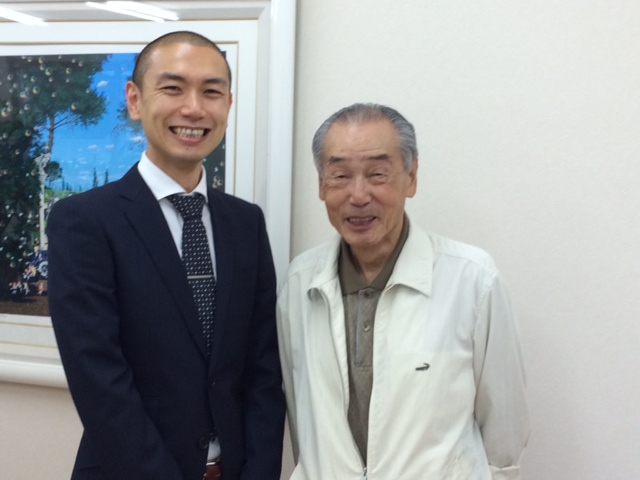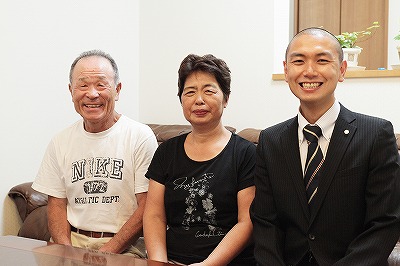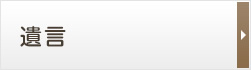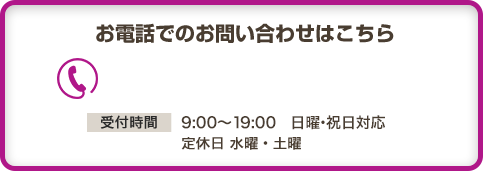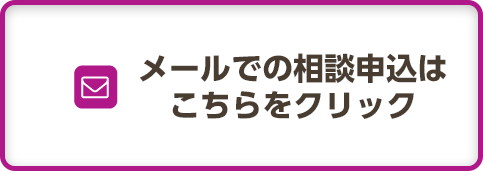【相続登記で起こりやすい漏れ・注意する土地】登記漏れ防止の確認方法等
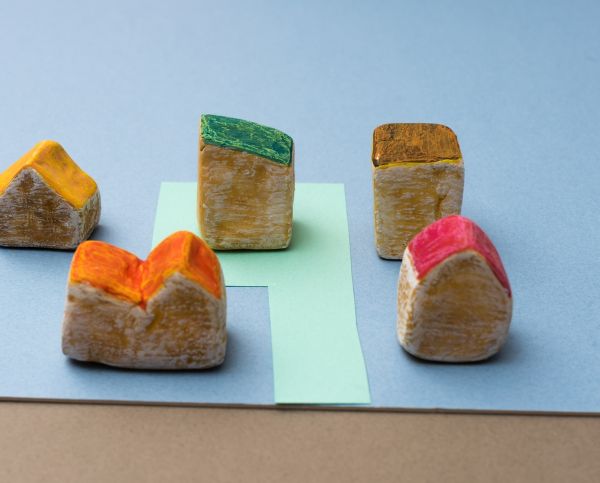
相続が発生したとき、忘れてはならないのが「不動産の相続登記」です。しかし、相続人の間で話し合いが終わっていたり、使用していない土地があったりすることで、登記手続きが漏れてしまうことも少なくありません。
この記事では、登記漏れが起こりやすい場面や注意すべき不動産の特徴、登記漏れを防ぐための確認ポイントなどを解説します。
相続登記をしていないことを発見するきっかけ
相続登記の未了(登記漏れ)は、当初は表面化せず、思わぬタイミングで発覚することがよくあります。以下のようなきっかけで「登記されていない不動産がある」と気づくケースが多いです。
・不動産を売却・担保設定しようとしたとき
不動産を第三者に売却したり、住宅ローンの担保として提供しようとした際、登記簿の名義が被相続人のままであることが分かり、初めて登記漏れに気づくことがあります。
・固定資産税の納税通知が届いたとき
市区町村から届いた納税通知書を確認すると、自分が把握していない土地が記載されており、「こんな土地があったのか」と驚かれる方も少なくありません。
・相続人がさらに亡くなり、次の相続手続きに進むとき
前の相続時に登記をしないまま放置していた場合、次の相続で手続きを進めようとして初めて登記漏れが判明することがあります。この場合、相続人が二代、三代と増えており、登記が非常に複雑になります。
・近隣住民や役所からの指摘
空き地や空き家が長期間放置されていた場合、近隣住民や自治体から管理状況についての問い合わせがあり、その調査過程で登記漏れが判明することもあります。
相続時に不動産登記漏れがあった場合の対処法
では、実際に相続時に不動産登記漏れがあった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。登記漏れの対処方法は、相続登記の根拠となる手続(=登記原因)によって異なります。
ここでは、代表的な3つのケースに分けて対処法を解説します。
遺産分割協議による登記の場合
相続人間で遺産分割協議書を作成して登記を行った場合、登記漏れとなっていた不動産がその協議書に記載されているかを確認することが出発点です。
・明確に記載がある場合
そのまま協議書の内容に従って、登記漏れの不動産についても追加で相続登記を行うことが可能です。
・記載がないが「その他の遺産」についての包括的な取り決めがある場合
たとえば「本協議書に記載のないその他の遺産は、長男〇〇がすべて取得する」などの包括条項がある場合、その記載を根拠にして、該当不動産の登記を行うことができます。
・当該不動産に関する記載が一切ない場合
明確な記載も包括条項も存在しないときは、再度相続人全員による遺産分割協議をやり直し、新たに協議書を作成する必要があります。この場合、登記手続に加えて、登記原因証明情報(新たな遺産分割協議書)や相続人全員の印鑑証明書が必要になります。
法定相続分による登記の場合
登記手続を「法定相続分どおり」に行っていた場合、登記漏れの不動産についても同様に法定相続分に従って登記するのが原則です。
後から新たに分割協議を行って持分の割合を変えることも可能ですが、その場合は再協議が必要となり、手間や調整が増えるため、実務ではあまり選択されません。
遺言による登記の場合
遺言書に基づいて相続登記を行っていたケースでは、登記漏れの不動産が遺言書に記載されているか否かが重要な判断基準となります。
・遺言書に当該不動産の明記がある場合
その内容に基づき、追加で相続登記を行うことが可能です。たとえば「〇〇市△△番地の土地は長女□□に相続させる」といった具体的な記載があれば、それを根拠に登記できます。
・記載はないが包括条項がある場合
たとえば「この遺言に記載されていない財産は長男△△にすべて相続させる」といった包括的記述がある場合は、それを根拠に登記することが可能です。
・記載も包括条項もない場合
この場合は、登記漏れの不動産については遺言の効力が及ばないため、相続人全員で遺産分割協議を行い、その内容を反映した新たな遺産分割協議書を作成する必要があります。
登記漏れになりやすい不動産とはどういうものか?
「存在に気づかなかった」「自分が所有しているとは思わなかった」といった理由で、相続登記が漏れてしまう不動産は少なくありません。
ここでは、登記漏れが起こりやすい不動産の代表例を具体的に紹介します。
私道(前面道路部分)
住宅の前にある道路が公道ではなく私道(私有地)だった場合、その道路部分について相続登記が必要となることがあります。私道の持分は周辺住民で共有していることが多く、被相続人がその一部を所有していたケースでは、「道路は公共のもの」と思い込んでいて相続対象と認識していないことが原因で登記漏れが起こります。
建物が建っていない土地(庭・空き地など)
住宅の敷地の一部にあたる「建物の建っていない部分」も、個別の地番で登記されている場合には、独立した土地として登記手続きが必要です。しかし、相続人は建物の登記だけで安心してしまい、付随する庭・駐車場などの土地の名義変更を忘れてしまうことがあります。
マンションの附属建物(物置・車庫・プレハブなど)
区分所有建物(マンション等)の中には、本体とは別に登記される附属建物があることがあります。たとえば物置や車庫、小屋などです。
これらの建物は「附属建物」として本体に付随する位置づけですが、登記上は別の家屋番号で登記されていることがあるため、注意が必要です。特にマンションの敷地内にある車庫が専用使用権付きで分譲されている場合などは、見落としやすいポイントです。
敷地権のないマンションの土地持分
現在の新築マンションでは「敷地権付き登記」が一般的ですが、築年数の古いマンションには土地と建物の登記が別々になっている物件も存在します。その場合、土地の登記簿上に複数筆の土地が含まれていたり、所有者が共有であるなどの事情により、一部の筆について相続登記がなされないまま放置されることがあります。
特殊用途の共有不動産(ごみ置き場・用水路・墓地など)
団地や分譲地などでは、地域全体で共有している特殊用途の土地があります。たとえば、ゴミステーション用地や用水路、町内墓地などです。
これらの土地も、被相続人が共有者の一人として持分を有していた可能性があるため、名寄帳や固定資産税課税明細書の確認時に漏れなく調査する必要があります。共有名義のまま放置されていると、次世代の相続人が登記できなくなるリスクが高まります。
共有名義で他の人が管理していた不動産
複数人で共有している不動産で、他の共有者が実際に管理していた場合、自分に持分があることを相続人が認識しておらず、登記手続きが漏れてしまうことがあります。たとえば、親族間での土地共有で「叔父が管理しているから関係ないと思っていた」などというケースです。
登記漏れを防止するために確認すること
相続登記の漏れを防ぐためには、被相続人が所有していた不動産をもれなく把握することが何よりも大切です。不動産は市区町村ごとに管理され、課税状況や登記の有無も物件ごとに異なるため、複数の資料を組み合わせて確認する必要があります。
以下では、代表的な3つの確認方法をご紹介します。
固定資産税の納税通知書を確認する
毎年春頃に自治体から送付される固定資産税納税通知書は、所有する不動産の所在地や面積、評価額などが記載された「課税明細書」が同封されており、不動産の洗い出しに有効です。
登記済権利証(登記識別情報)を確認する
不動産を取得した際に発行される「登記済権利証」や「登記識別情報通知」は、対象不動産の登記内容を確認するための有力な手がかりになります。これらには、登記された物件の所在・地番・種類などが明記されています。
名寄帳を取得して確認する
名寄帳(なよせちょう)とは、1つの市区町村にある不動産を所有者ごとにまとめて一覧表示した帳票です。土地や建物の所在地・地番・面積・評価額などが記載され、非課税の不動産も掲載されるため、登記漏れの発見に非常に有効です。
登記漏れの土地・建物があった場合の注意点
ここでは、登記漏れがあった場合に注意すべきポイントを解説します。
未登記の不動産はそのままでは使えない
登記されていない不動産は、法的には名義が確定していない状態であり、第三者に対して所有権を主張することが困難です。たとえば以下のような制限が生じます。
- 売却や贈与、担保設定などの処分行為ができない
- 名義人が被相続人のままのため、取引先や第三者に対して所有権を主張できない
- 住宅ローンが組めない、相続人間での分配も困難になる
不動産を適切に相続・管理するためには、登記による名義変更が不可欠です。
相続登記の義務化と過料制度に注意
2024年4月1日から、相続登記は法律上の義務となりました。これにより、相続によって不動産を取得した人は、その事実を知った日から3年以内に登記申請をしなければならないとされています。
もし正当な理由なくこの義務に違反した場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。また、未登記建物を取得した場合には、別途表題登記の義務もあり、こちらも怠ると同様に罰則の対象になります。
放置すると相続関係が複雑になりやすい
登記漏れを放置したまま相続人の一人が亡くなると、その人の相続人も新たに権利関係に関わることになり、「数次相続」の状態になります。
たとえば、最初の登記漏れの時点では3人だった相続人が、次の代でその子や配偶者に引き継がれ、関係者が10人以上になることも珍しくありません。このような状態になると
- すべての関係者の戸籍の取得
- 全員による遺産分割協議
- 一部の所在不明者への対応(失踪宣告・不在者財産管理など)
といった手続きが必要になり、実質的に登記ができなくなるケースもあります。
司法書士に相談
登記漏れの不動産が見つかったとき、「何から手を付ければよいのかわからない」「そもそも自分たちでできるのか不安」と感じる方も多いのではないでしょうか。
こうした場面で頼りになるのが、相続登記の専門家である司法書士です。司法書士は、不動産の調査や必要書類の収集、登記申請書の作成はもちろん、法務局への提出や相続人への説明調整など、煩雑な手続きを一括して代行することができます。
「登記のことは難しい」「このままで大丈夫か心配」という方こそ、一人で悩まず、まずは司法書士にご相談ください。状況に応じた最善の対応方法を一緒に考え、丁寧にサポートいたします。