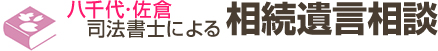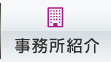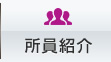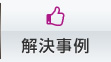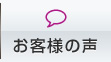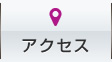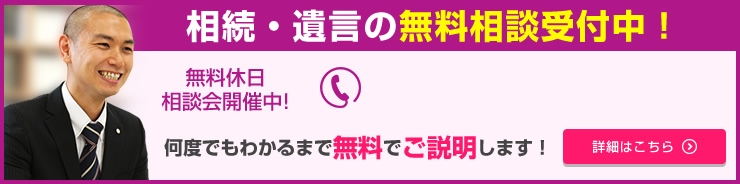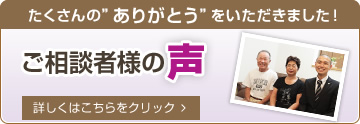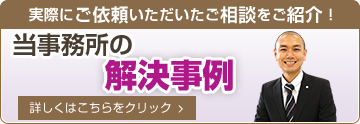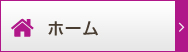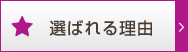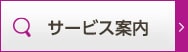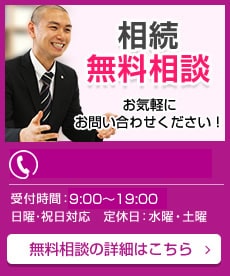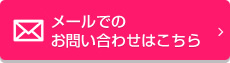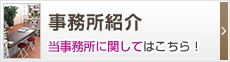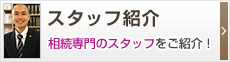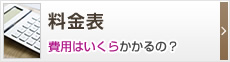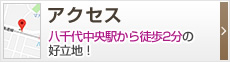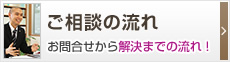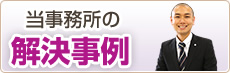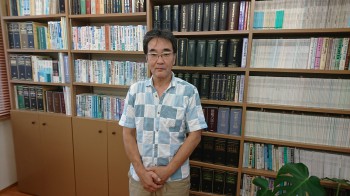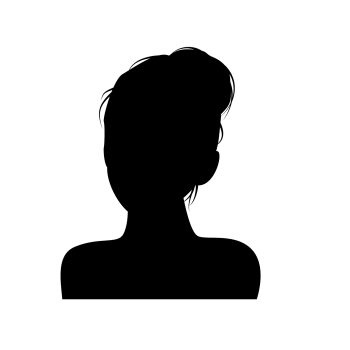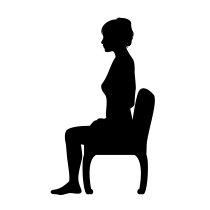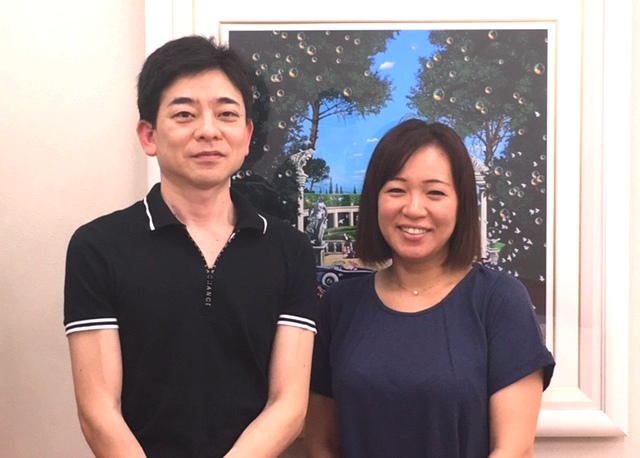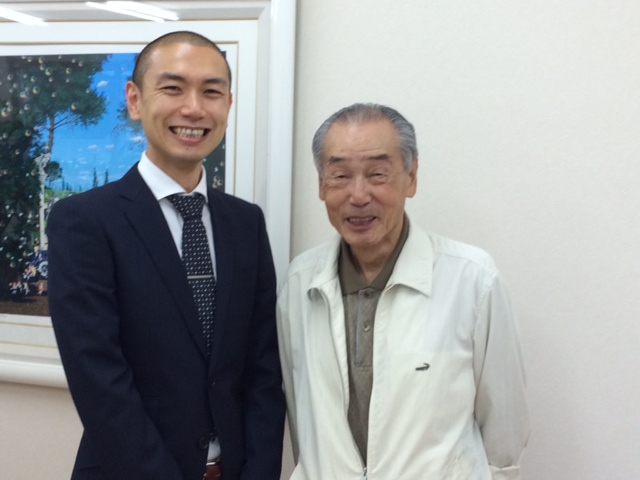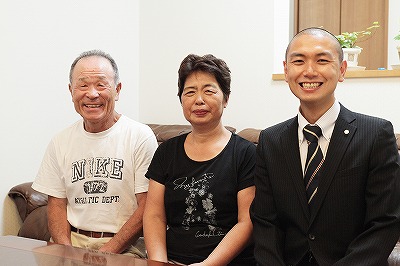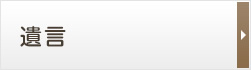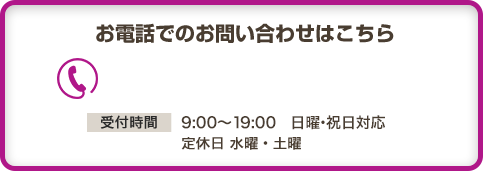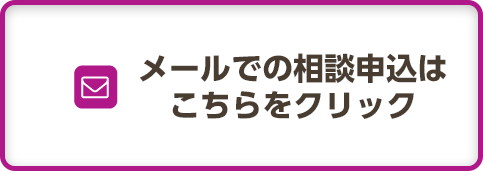【相続放棄と生命保険】相続放棄をすると生命保険を受け取れないことがあるので要注意!相続税にも注意しましょう

例えば、父親が亡くなって、多額の借金を抱えていたことがわかりました。
相続放棄をした場合、亡くなった父親が生命保険をかけている場合に、受け取ることができなくなるのではないか?
こんな不安をお持ちの方もいらっしゃると思います。
また、生命保険金を受け取った場合の相続税について、ご心配な方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、相続放棄をした場合に生命保険金を受け取ることができるか、受け取ることができる場合、相続税はどうなるのかといったことについて解説していきます。
1 相続放棄とは
まず、最初に、相続放棄の基本事項について解説します。
1-1 相続放棄の定義
相続放棄とは、相続の際に相続人の資産や負債などの財産全てに対する権利や義務を一切引き継がず放棄することです。
例えば、被相続人の遺産に借金が含まれる場合には、相続放棄をすることにより引き継がなくてよくなります。
しかし一方で、相続人の資産も引き継ぐことができなくなります。
1-2 相続放棄の手続
相続放棄は、裁判所に対して申述をすることによって行います。
相続放棄の手続ができる期間は、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」とされています。
申立ての際には、申述書の他に戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票、相続関係図などを添付します。
申述が認められると、家庭裁判所から、申述受理の通知書が送付されてきます。これにより手続きは終了します。
2 相続放棄をしても生命保険金は受け取れるものなのか?根拠は?
先ほど、相続放棄をすると相続人の資産に対する権利を一切引き継ぐことができないと解説しました。
そのため、相続放棄をすると生命保険金が受け取れなくなると考えられがちです。
しかし、以下の場合には、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。
2-1 死亡保険金
受取人が定められている死亡保険金については、相続財産に該当せず、受取人の固有の財産となるため、相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。(言葉が本当に難しいですね…。ここでいう相続財産は、民法の話で、税法の話では、みなし相続財産に該当します。相続は、民法と税法が絡み合いますので、相続財産という言葉1つとっても、しっかり理解していないと、大きな間違いが生じます。よくある勘違いが、『死亡保険金は相続財産じゃないなら、相続税の申告には計上しなくて良いんでしょ』といった感じです。)
更に、受取人が相続人と記載されている死亡保険金についても、相続人それぞれの氏名が記載されているのと同じと考えますので、相続人が相続放棄をしても保険金を受け取ることが可能です。
上記と似た様なケースですが、生命保険金の受取人が被保険者よりも先に亡くなっていた場合、受取人の相続人が生命保険金の受取人となります。
この場合、生命保険金は受取人の相続人の固有の財産となるため、相続放棄をしても、受け取ることが可能です。
相続人が複数の場合には、受け取れる金額は法定相続分に関わらず、相続人の頭割りとなります。
被相続人に借金があっても、相続放棄をすれば、生命保険金の中から借金を支払う必要もありません。
3 相続放棄をすると生命保険金を受け取ることができない場合
先ほども説明したように、原則的には相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができますが、以下の場合は受け取ることができません。
3-1 受取人が被相続人の場合
生命保険金の受取人が被相続人に指定されている場合は、その相続人が相続放棄をすると、生命保険金を受け取ることができません。
この場合、生命保険金は、亡くなった人の財産として扱われることになるため、相続放棄をすると引き継ぐことができなくなってしまうのです。
老後のための貯蓄を兼ねている生命保険の場合は、契約者本人が受取人に指定されていることも少なくありません。
そのため、このようなケースでは、受取人が亡くなるとこれらの保険金は被相続人本人の財産と扱われることとなり、相続放棄の対象財産となります。そのため、相続放棄をすると受け取ることができなくなります。
相続放棄をした場合には、生命保険金の受取人が誰であるかを確認しておくことが必要です。
3-2 債権者に差し押さえられた場合
また、被相続人に借金があり、債権者が訴訟を起こして確定判決を有している場合や、被相続人と債権者が公正証書を作成しており、その中に強制執行認諾文言がある場合には、生前に生命保険を解約し、その解約返戻金を差し押さえられてしまうことがあります。
この場合には、被相続人が亡くなった時点で、生命保険金は残っていないこととなるので、仮に受取人が相続人に指定されていたとしても、受け取ることができなくなります。
ただし、平成22年に保険法が施行された際に、保険金の受取人が解約返戻金相当額を債権者に支払うことで保険契約を解約せずに存続することを可能にする「介入権」という制度が設けられました。
介入権を受取人が行使した場合には、保険契約は解約されずに存続することとなります。
3-3 その他
3-3-1 解約返戻金
解約返戻金は、保険契約者の財産となります。
そのため、保険契約者の死亡後に相続人が相続放棄を行うと、解約返戻金を受け取る権利も喪失するため、受け取ることができなくなります。
3-3-2 満期返礼金
満期返戻金とは、契約が満期までに有効に存続し、保険料の張り込みを全て終えている場合、満期時に保険会社から保険契約者に対して支払われるものです。
そのため、保険契約者が死亡し、その相続人が相続放棄をした場合には、満期返戻金請求権を相続することができず、満期返戻金を受け取ることができません。
3-2-3 据え置き金
据え置き金とは、満期保険金や死亡保険金等の全部または一部を、保険会社が所定の利息をつけて預かっているものです。
満期保険金は保険契約者に受け取る権利があり、死亡保険金は受取人に権利があります。
そのため、据え置き金が満期保険金の場合には、その請求権は相続財産になるため、保険契約者の相続人が相続放棄をした場合には、これを受け取ることができません。
3-2-4 医療保険
医療保険に基づき、被相続人が未請求だった入院給付金や手術給付金等があった場合、相続放棄をした後でこれを受け取れるかも問題となります。
入院給付金や手術給付金等は被相続人が受け取るべきお金であり、その請求権は被相続人にあります。すなわち、医療保険に基づく入院給付金や手術給付金等の請求権は相続の対象となります。
そのため、相続放棄をすると、これらの請求権も放棄したこととなり、相続人は入院給付金や手術給付金などを受け取ることができなくなります。
4 相続放棄をして、生命保険金を受け取る場合の注意点
相続放棄をしたうえで、生命保険金を受け取る場合には、相続税について注意が必要です。
生命保険には、通常保険金の受取人1人に対して500万円の非課税枠が設けられています。
例えば、保険金が6000万円で受取人が2人指定されている場合、6000万円-500万円×2の5000万円が課税対象となります。
生命保険は遺族の生活を保障するためのサービスであるため、遺族の負担軽減のために非課税枠が設けられました。
しかし、相続放棄をしてしまうと、非課税枠は適用されません。
そのため、上記の例のケースでは、保険金6000万円全額が相続税の対象となります。
5 まとめ
今回は、相続放棄と生命保険金の関係について解説しました。
相続放棄ができる期間は相続開始を知ったときから3か月に限られています。
迅速な対応が必要であることを忘れないようにしてください。
当事務所では、相続放棄に関するご相談をお受けしております。