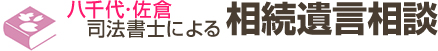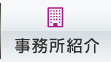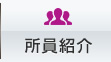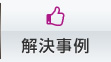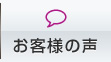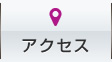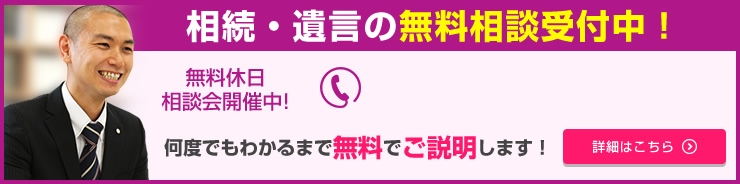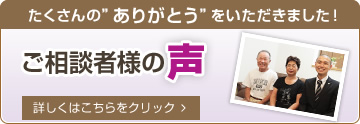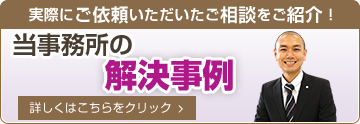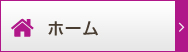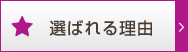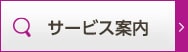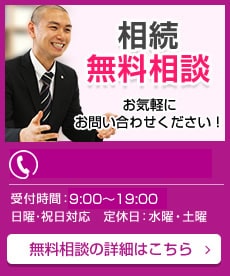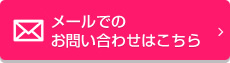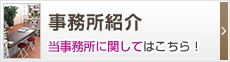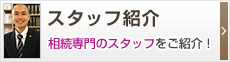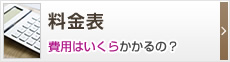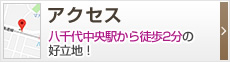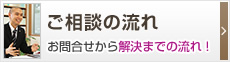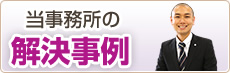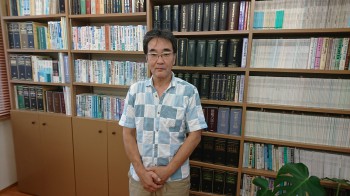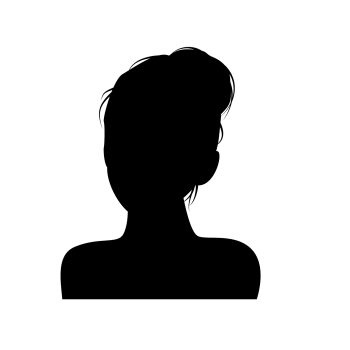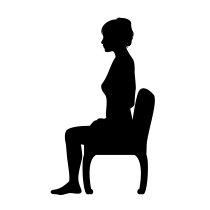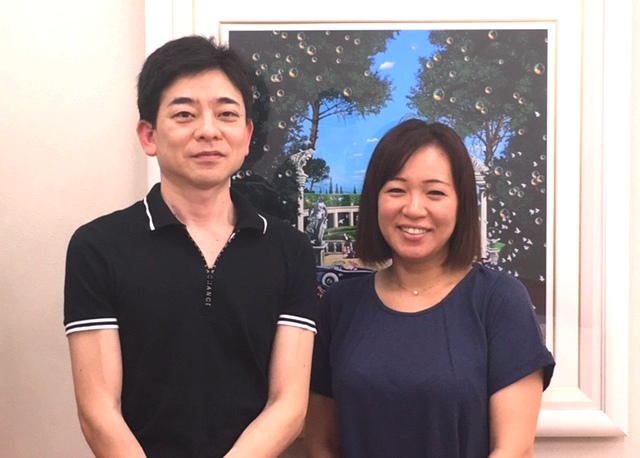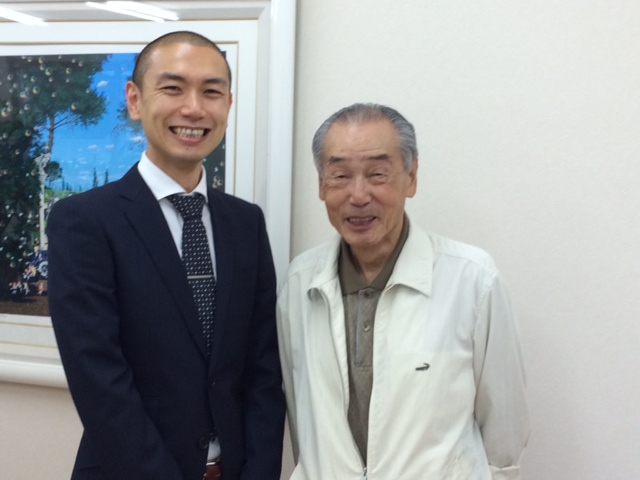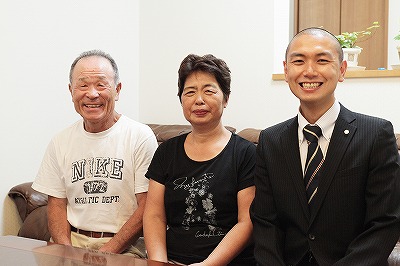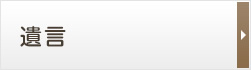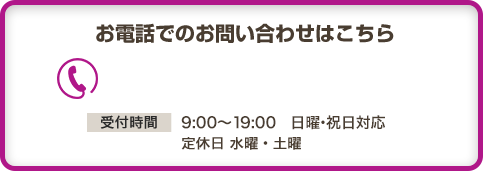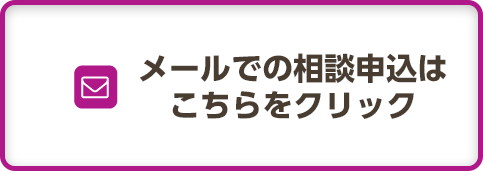【生命保険は相続財産?】特別受益との関係、受取人が先に死亡していた場合など解説

親族が亡くなった際、生命保険の死亡保険金を受け取れることがあります。その際、気になるのは相続と保険金との関係について疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、死亡保険金が相続財産に含まれるかどうか、税金との関係、特別受益になる可能性、受取人が先に亡くなっていた場合など、よくあるケースごとに詳しく解説します。
相続における死亡保険金の扱い
生命保険の死亡保険金は、原則として相続財産には含まれません。
保険金は保険契約に基づいて、あらかじめ指定された受取人が受け取るものであり、被相続人の財産ではなく、法律上「受取人固有の財産」とされています。そのため、遺産分割の対象にもなりません。
したがって、受け取った保険金を他の相続人に分配する必要もありませんし、遺産分割協議書を作成する場合でも、死亡保険金について記載する必要はありません。
ただし、税務上は、「みなし相続財産」として、相続税の課税対象となることがあります。次に、その点を詳しく見ていきましょう。
死亡保険金に相続税がかかるのはどんなとき?
死亡保険金は民法上は相続財産に含まれませんが、税務上は「みなし相続財産」として扱われることがあります。
みなし相続財産とは、相続によって取得したわけではないものの、被相続人の死亡によって発生した財産のことです。生命保険金や死亡退職金などが該当します。
被相続人が保険料を支払っていた場合、その死亡保険金はみなし相続財産となり、他の財産と合算して相続税の課税対象になります。
ただし、死亡保険金には「非課税枠」が設定されています。受取人が相続人である場合、「500万円×法定相続人の数」までが非課税となります。
一方、保険料の支払者が被相続人でない場合には、死亡保険金は相続税の対象外となり、代わりに、所得税や贈与税が課されます。
- 所得税がかかるケース:保険料負担者と受取人が同じ人の場合
- 贈与税がかかるケース:契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合
高額な死亡保険金が特別受益として扱われる可能性は?
「特別受益」という言葉を聞いたことがある方は、死亡保険金がそれに該当するのではないか?と不安に思っているかもしれません。その点について解説します。
特別受益とは?
複数の相続人の中で、特定の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈などで多くの財産を受け取っている場合に、相続時にその利益を考慮しないと不公平になることがあります。こうした利益を「特別受益」といいます。
たとえば、相続人が長男・長女・次男の3人で、遺産総額が6,000万円あるとします。通常であれば、各人の法定相続分は3分の1ずつ、すなわち2,000万円ずつです。
ところが、長男が生前に1,200万円の贈与を受けていた場合、そのまま分けると「贈与1,200万円+相続2,000万円=合計3,200万円」となり、長男だけが多く受け取ることになってしまいます。
このような不公平を調整するために、特別受益は一度遺産に「持ち戻し」して計算されます。
今回の例では「6,000万円+1,200万円=7,200万円」として3人で分け直すと、各人の相続分は2,400万円になります。長男は既に1,200万円を受け取っているので、相続で受け取れるのは1,200万円となります。
このように、特別受益を考慮することで、相続人間の公平が図られるのです。
特別受益と死亡保険金の関係
原則としては死亡保険金は特別受益には該当しません。
その理由は、死亡保険金は相続によって承継されるのではなく、保険契約に基づき受取人が固有の権利として取得するものだからです。
ただし、最高裁判所の判例では、例外的に相続人間で著しい不公平が生じる事情がある場合には、死亡保険金が特別受益として認められることもあるとしました。
その判断にあたっては、
- 保険金の額
- 保険金額の遺産の総額に対する比率
- 同居の有無
- 亡くなった人の介護等に対する貢献の度合いなど、生前の関係性
- 各相続人の生活実態
などのさまざまな要素を総合的に考慮するとされています。
特別受益に関する判断の具体例
ここでは、特別受益に関する判断をした判例を紹介します。
① 広島高裁令和4年9月8日判決
- 相続財産:約459万円
- 死亡保険金:約2,100万円(約4.6倍)
- 結果:特別受益に当たらないと判断。
【理由】
- 一般的な夫婦間での保険金額の相場や、亡くなった人の収入に対する保険料の額から見て、あまりにも多すぎるとは言えないこと
- 遺された妻が長い間一貫して専業主婦で、他に収入がなかったこと
- 妻は50代で収入がなく、保険金による長期間の生活保障が必要。これに対して、特別受益を主張していた母は他の人からの遺産があり、生活に困る状況ではないこと
② 東京高裁平成17年9月16日判決
- 相続財産:7,700万円
- 死亡保険金:5,000万円(遺産の約65%)
- 結果:特別受益に当たると判断。
【理由】
- 婚姻期間が短かった
- 保険金額が5000万円以上の高額だった
- 保険金の取得により他の相続人との間に著しい不公平が生じる
③ 名古屋高裁平成18年9月14日判決
- 相続財産:約2,400万円
- 死亡保険金:約1,500万円(遺産の61%)
- 結果:特別受益に当たると判断。
【理由】
- 他にも特別受益者がいて、保険金額がその特別受益額よりも大きかった
- 介護中も含め、生活費は亡くなった人の収入で賄えていた(保険金による生活保障の必要性が薄かった)
- 保険金受取人に全財産を相続させる遺言があった
このように、特別受益かどうかは、必ずしも金額や割合だけで判断できるものではありません。保険金を受け取ることで特別受益の主張をされる心配がある場合には、あらかじめ専門家に相談するのが良いでしょう。
保険金の受取人が被相続人より先に死亡していた場合
死亡保険金の受取人として指定されていた人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合には、どうなるでしょうか。
原則として相続人が受け取る
死亡保険金の受取人として指定されていた人が、被相続人よりも先に亡くなっていた場合にはどうなるのでしょうか。
原則として、その受取人の相続人が死亡保険金を受け取ることになります。受取人の相続人が複数いる場合には、単純に頭割り(2人なら2分の1ずつ、3人なら3分の1ずつ)で支払われるのが一般的です。
ただし、これはあくまで一般的な取扱いであり、保険会社ごとの約款で特別なルールが定められている場合は、そのルールが優先されます。実際に、受取人がすでに亡くなっていることが判明したときは、まず保険会社に支払条件を確認するのが安心です。
相続税額が増えてしまうことはある
受取人の相続人が受け取る場合、相続税が二重にかかるのではないかと心配になる方もいるでしょう。これは、一度受取人に課税され、その後さらに受取人の相続人にも課税されるように思えてしまうからです。
しかし実際にはそうではなく、死亡保険金は最初から「受取人の相続人」が直接受け取るものと扱われます。そのため、課税されるのは一度だけで、二重に相続税がかかることはありません。
ただし、受取人の相続人が死亡保険金を受け取る際は、相続税の額については注意が必要です。これは、相続税の非課税枠や2割加算の適用が、「今回亡くなった被相続人との関係」で判断されるからです。
具体例でみてみましょう。
【例1:受取人の相続人が、被相続人の相続人ではないケース」
父を被保険者として契約し、受取人を「子」としていた場合を考えます。ところが、その子が被保険者より先に亡くなり、残された「子の配偶者(義理の娘・息子)」が受取人の相続人として保険金を受け取ったとします。
この「子の配偶者」は、被相続人(父)から見れば相続人ではありません。そのため、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が使えなくなり、税額が大きくなる可能性があります。
【例2:相続税の2割加算の対象になるケース】
例1と同じ状況の場合、子の配偶者は被相続人(父)から見て直系親族ではないため、「相続税の2割加算」の対象にもなります。
これは、相続税法で「被相続人から見て、配偶者・父母・子、または代襲相続する直系親族」以外の人が財産を取得したときには、本来の相続税額に加えて20%上乗せされる、と定められているからです。つまり、被相続人からみて「義理の娘・息子」は直系親族ではないため、2割加算の対象になってしまうのです。
相続放棄をした場合でも、死亡保険金は受け取れるのか?
相続放棄を検討していて、死亡保険金の受取人でもある、という場合、もし相続放棄をしたら死亡保険金も受け取れなくなるのかどうかが、選択に大きく影響するでしょう。
相続放棄をしても、死亡保険金は受け取れます。
ここでは、死亡保険金は本来の意味での相続財産ではない、という原理原則が優先されます。相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができるのです。
相続税額には注意が必要
保険金を受け取りつつ相続放棄をするときは、税金についても考慮すべきです。
まず、相続放棄をした人は、「法定相続人」ではないとみなされるため、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)の適用がなくなります。
さらに、被相続人の配偶者・父母・子以外の人が相続放棄をした上で死亡保険金を受け取ると、相続税が2割加算されてしまいます。たとえば兄弟や第三者が受け取る場合がこれにあたります。
なお、代襲相続人である孫が死亡保険金を受け取る場合、相続放棄をするかどうかによって、相続税の2割加算の対象になるかどうかが変わる点に注意が必要です。
たとえば、本来の相続人である被相続人の「子」がすでに亡くなっており、孫が代襲相続人として死亡保険金を受け取る場合、孫は「子の代わり」として相続する立場になります。この場合は、孫も一親等の血族と同じ扱いとなるため、2割加算の対象にはなりません。
しかし、その孫が相続放棄をした場合は話が変わります。孫は代襲相続人ではなくなり、単に「被相続人から見た孫」という立場になります。この場合は一親等の血族ではないと見なされ、相続税が2割加算されてしまいます。
相続放棄は、税金が増加するリスクも考えた上で決定するのが良いでしょう。亡くなった方との関係性が複雑であるときは、専門家に相談してください。
迷ったら司法書士に相談しよう
死亡保険金に関して、ここで解説した以外にも複雑な状況はたくさんあります。
「自分の場合にどれが当てはまるのか分からない」
「記事を読んだだけで決めるのは不安」
「結局、どうすればいいの?」
迷いや不安があるときは、まずは司法書士に相談してみましょう。
相続に関し豊富な知識を持つ専門家が、複雑な状況を解きほぐし、最適解を見つけるお手伝いをします。もちろん、手続き面のサポートも万全です。