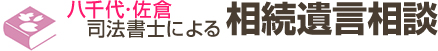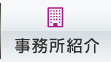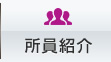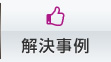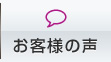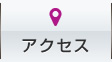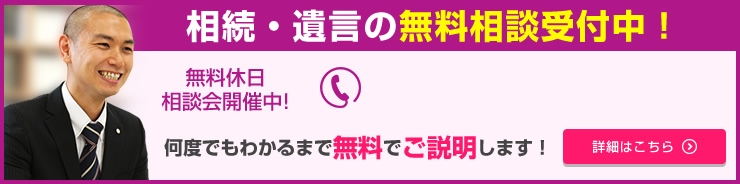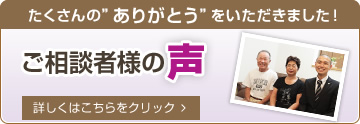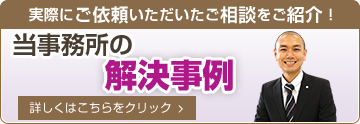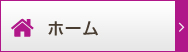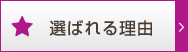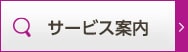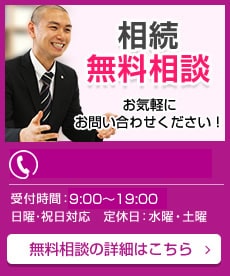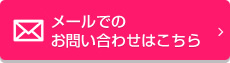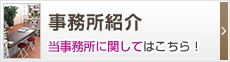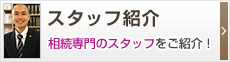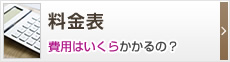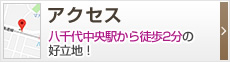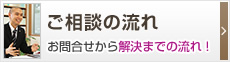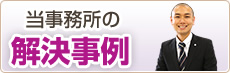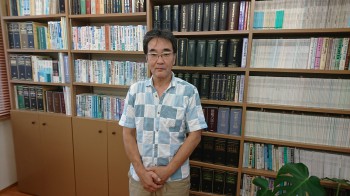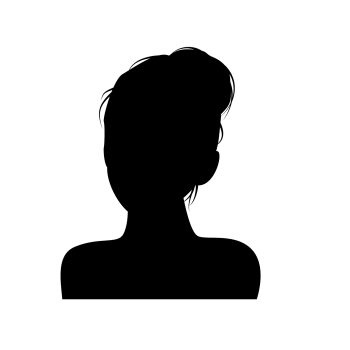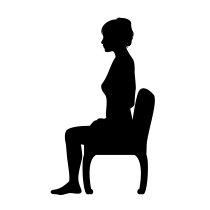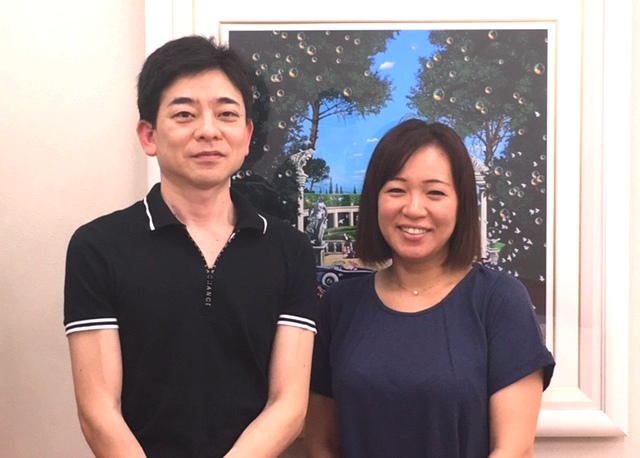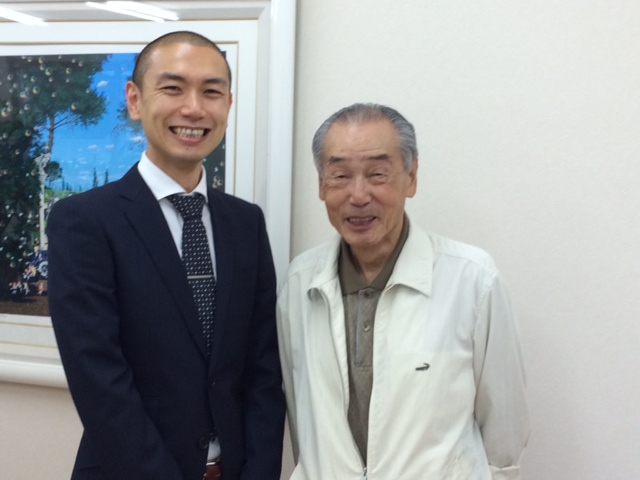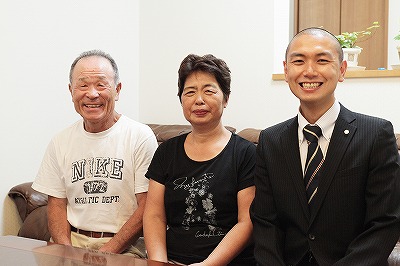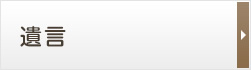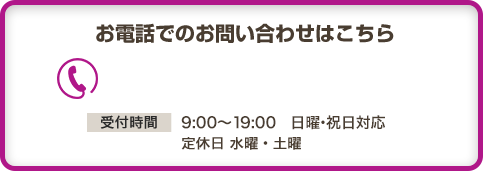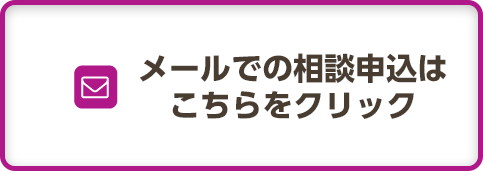知らないと大損!相続税の計算で使える「家なき子の特例」適用条件とは

実家を相続したけれど、親と同居していなかったから「小規模宅地等の特例」は使えないと諦めていませんか?
そんなときに知っておきたいのが、通称「家なき子の特例」。特定の条件を満たせば、非同居の相続人でも土地の評価額を大きく減額でき、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
この記事では、この家なき子の特例の概要や適用条件、活用する際の注意点までをわかりやすく解説します。
そもそも「家なき子の特例」とは?
「家なき子の特例」とは、親と別居していた子どもが実家の土地を相続したときに、一定の条件を満たせば大幅に軽減される制度です。
通常、親と同居していた子どもが実家の土地を相続する場合は「小規模宅地等の特例」が使え、土地の評価額を大きく下げることができます。しかし、「実家を離れてずっと賃貸暮らしだった」「遠方に住んでいた」など、非同居の相続人だと原則としてこの特例は適用されません。
そこで登場するのが「家なき子の特例」です。持ち家を持たず、他人の家や賃貸に住んでいた相続人であれば、一定の条件下でこの特例が認められる場合があります。うまく適用できれば、相続税の負担が何百万円単位で変わることも。
この「家なき子の特例」という名称はあくまで通称で、法律上の正式名称ではありません。正確には、「小規模宅地等の特例」のなかでも、非同居親族に対する適用要件を指すケースを、実務上まとめてこう呼んでいます。
そもそも「小規模宅地等の特例」とは?
「家なき子の特例」は、「小規模宅地等の特例」という制度の一部に該当します。
「小規模宅地等の特例」とは、被相続人(亡くなった方)が居住または事業に使用していた宅地について、土地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。土地の評価額が相続税額に直結することから、非常に大きな節税効果があります。
たとえば、1,000万円と評価される宅地にこの特例を適用すれば、評価額は200万円にまで下がり、その分相続税も大幅に減額されます。
この特例は、主に「配偶者」や「同居していた親族」に適用されます。実家で親と一緒に暮らしていた子どもがそのまま土地を引き継ぐ場合などが典型です。
「家なき子の特例」は小規模宅地の特例を“非同居でも”使えるようにしたもの
「小規模宅地等の特例」は、もともと被相続人と同居していた親族が対象とされていました。つまり、「一緒に住んでいた人がその家を相続するなら、相続税は軽くしてあげますよ」という考え方です。
しかし現代では、仕事や結婚などを理由に、親と別居して暮らす子どもも多くなっています。こうした状況に対応するために設けられたのが、「家なき子の特例」です。
これは、持ち家を持たず、賃貸住宅や社宅などに住んでいた相続人が親の自宅を相続する場合、一定の要件を満たせば、非同居でも小規模宅地等の特例を使えるという制度です。
つまり、「親と同居していなかった=特例の対象外」とは限らないということ。“自分の家を持っていなかったこと”が、大きなポイントです。
ただし、この制度はあくまで“例外的な措置”です。誰でも簡単に使えるものではなく、細かな条件をクリアする必要があります。
次の章では、その適用条件について詳しく見ていきましょう。
特例を適用するための条件
「家なき子の特例」を使って相続税の負担を軽くするには、4つの厳しい条件をすべて満たす必要があります。どれか1つでも欠けると、特例は適用できません。制度の趣旨を理解し、適用の可否を慎重に確認することが重要です。
① 被相続人に配偶者や同居している相続人がいない
まず重要なのが、相続される側、つまり被相続人に「配偶者」または「同居している相続人」がいないことです。このどちらかでも存在する場合は、そちらに小規模宅地等の特例が適用されるのが原則で、「家なき子の特例」は使えません。
ここで気をつけたいのが、「別居していれば配偶者はカウントされない」という誤解です。たとえ長年別居していても、戸籍上の配偶者がいる限り、「配偶者あり」と判断されるため、特例は使えません。
② 相続開始前の3年間、持ち家に住んでいない
次に大事なのは、「相続人自身や配偶者が、過去3年以内に一定の持ち家に住んでいなかったか」という点です。
この“持ち家”には、以下が含まれます。
- 自分自身の所有する家
- 配偶者の所有する家
- 3親等以内の親族(親・子・兄弟姉妹・甥姪など)の家
- 特別な関係にある法人が所有する家
たとえば、「夫名義のマイホームに住んでいる妻」は、自分が所有していなくても条件に当てはまってしまうため、家なき子の特例は使えません。
一方で、「いとこ(=4親等)名義の家」に住んでいた場合は、要件に該当せず、特例の対象になる可能性があります。
③ 相続した宅地を10か月間、所有し続けている
家なき子の特例を受けるには、相続税の申告期限(相続開始から10か月)まで、対象の土地を所有し続ける必要があります。
売却してしまうとこの要件を満たさなくなるため、途中で土地を処分した場合は、特例が適用できなくなります。なお、申告期限内に「貸す」だけであれば、所有している状態なので要件はクリアされます。
④ 現在住んでいる家を、これまで所有したことがない
最後の条件は、相続開始時に居住している家屋を、過去に一度も所有したことがないこと。
これは平成30年の税制改正で新たに加えられた条件です。というのも、過去にはこんな“節税テクニック”が横行していました。
- 自分の持ち家を名義だけ他人(子や孫)に移して、「持ち家がない」状態を演出
- リースバックで家を売却してから自宅に住み続け、「家なき子」を装う
このように、形式的に「家がない」と見せかけて特例の適用を受けるケースが増えたため、制度が見直され、過去に所有歴がある家に住んでいた場合は対象外となりました。
家なき子の特例が使える代表的なケース
家なき子の特例は、適用されれば相続税の大幅な軽減が期待できる制度です。ただし、すべての相続に適用されるわけではなく、一定の条件を満たす場合に限られます。
ここでは、実務でよく見られるケースをご紹介します。ご自身の状況が該当するかどうか、判断の参考にしてください。
ケース①:賃貸暮らしの子どもが実家を相続する
地方に住む親が亡くなり、東京など都市部で賃貸暮らしをしていた子どもが実家を相続するケースは非常に多く見られます。
たとえば、次のようなケースです。
- 実家には一人暮らしの母が住んでいたが、亡くなった
- 子どもは10年以上、都市部の賃貸マンションで生活している
- 相続後はしばらく実家を空き家として保有している、または住み始める
このような場合、比較的スムーズに特例の適用を受けられるケースが多いといえます。
ケース②:不動産を複数所有しているが、自宅は賃貸のまま
相続人が自宅を持っていないものの、収益用の物件や別荘などを複数所有しているケースも見られます。
たとえば、次のようなケースです。
- 本人名義のワンルームマンションを複数所有している
- 自身は賃貸マンションに住み続けている
- 投資用不動産には一切居住していない
このような場合、収益用物件に居住していなければ、家なき子の特例の対象となる可能性があります。ただし、過去に一度でも自ら居住していた場合や、名義変更によって居住歴を隠すような動きがある場合には、特例の適用が否定されるリスクもあるため注意が必要です。
ケース③:相続開始後に住宅を取得した場合
相続開始時点では持ち家がなく、賃貸住宅に居住していた相続人が、その後、住宅を購入するケースもあります。このような場合でも、相続開始の時点で「家を持っていなかった」ことが確認できれば、家なき子の特例の適用は可能です。
たとえば、次のようなケースです。
- 親の死後、しばらくしてから新たに自宅を購入した
- 相続開始時は賃貸マンションに住んでいた
- 相続した実家には住まず、新居を購入して転居した
このような状況であっても、特例の要件を満たしていれば適用の可能性があります。
また、相続後にその宅地へ居住し始めた場合でも、家なき子の特例の適用に支障はありません。この制度で重視されるのは、「相続が始まるまでの3年間に、どこで・どのように暮らしていたか」という点です。
特例を活用するための注意点と専門家への相談
家なき子の特例を適用するには、制度上の要件を満たすことに加えて、申告の手続きも正確に行う必要があります。ここでは、申告時に特に注意すべきポイントをまとめます。
相続税の申告は必須です
家なき子の特例を受けるには、非課税であっても相続税の申告が必要です。申告しなければ、特例の適用は認められません。
申告期限は、被相続人が亡くなった日から10か月以内。期限を過ぎると、加算税や延滞税が発生する可能性もあるため、早めの準備が重要です。
添付書類はやや複雑になる
家なき子の特例の適用を受けるには、以下のような資料の提出が求められます。
- 過去の住所を示す戸籍の附票やマイナンバーカードの写し
- 賃貸借契約書、不動産登記簿など、居住実態を証明する書類
- 過去に所有していた家がないことの証明資料
同居親族と比べて、非同居親族は提出書類が多くなりやすいため、事前に必要な書類を確認しておくことが大切です。
専門家への相談が安心につながります
家なき子の特例の適用は、制度の解釈や状況の判断が難しいケースも多くあります。また、不動産の評価方法によって相続税額が大きく変わる可能性もあります。
こうしたリスクを避け、確実に特例を活用するためには、早い段階で専門家に相談するのが安心です。
はながすみ司法書士事務所では、家なき子の特例をはじめとした相続対策について、税理士と一緒に手続きを行えますので、お気軽にご相談ください。