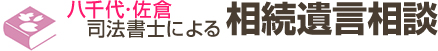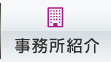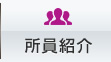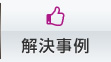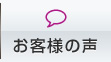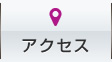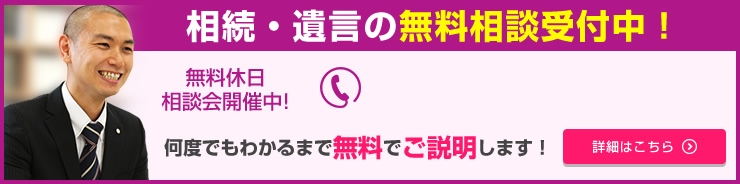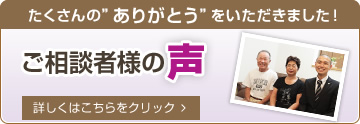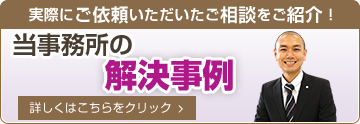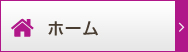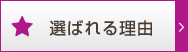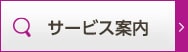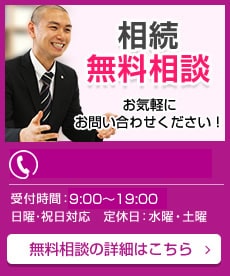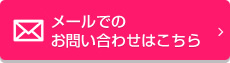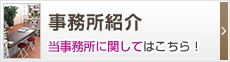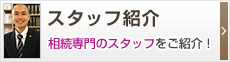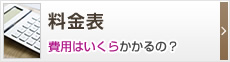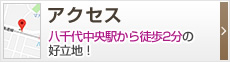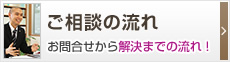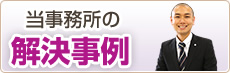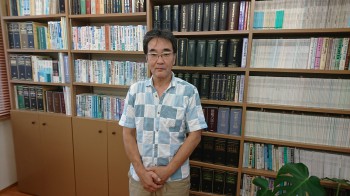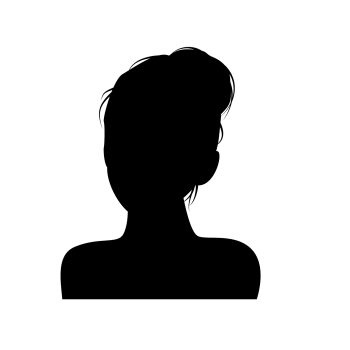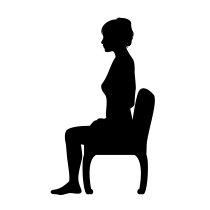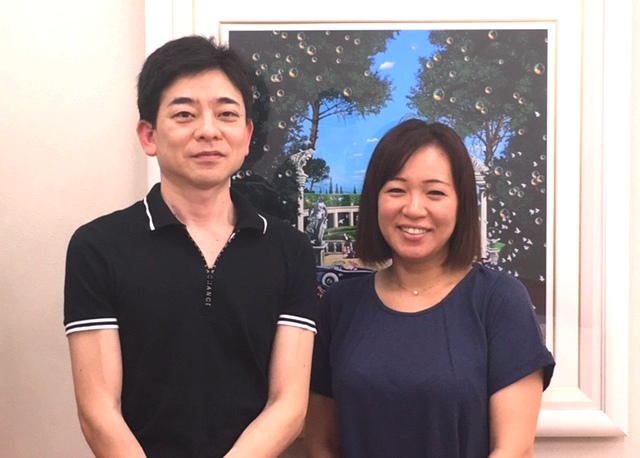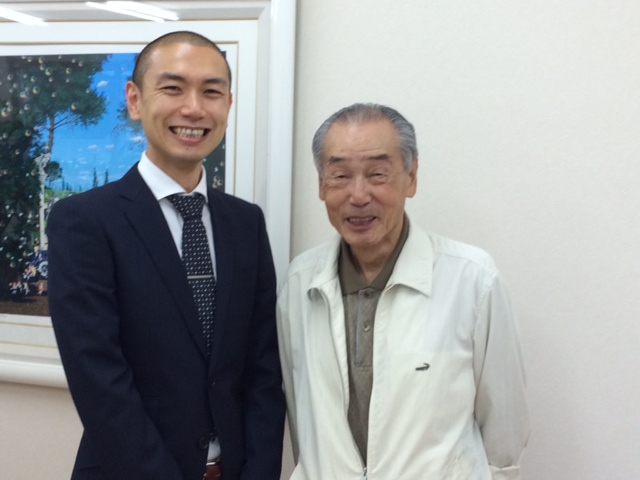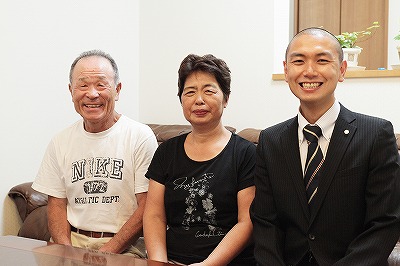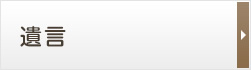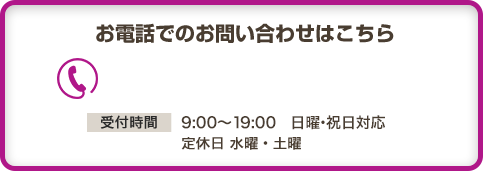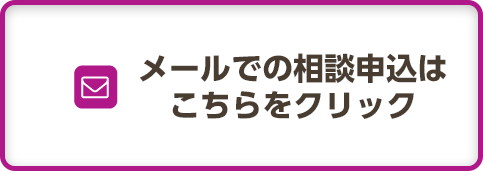2025年10月施行!公正証書遺言のオンライン作成(デジタル化)完全ガイド

2025年10月から、公正証書遺言の作成手続きがついにデジタル化されます。
これまでは公証役場に出向く必要がありましたが、今後はパソコンを使ってオンラインで完結できるケースが出てきます。本人確認や手続きの一部をウェブ会議で行うことも可能になり、より柔軟で負担の少ない制度へと進化します。
このオンライン化により、遺言作成がこれまで以上に身近なものとなり、「いつかは」と思いながら先延ばしにしていた方にとっても、一歩を踏み出しやすい環境が整います。
この記事では、公正証書遺言のデジタル化が実現する背景や変更点、具体的な手続きの流れ、注意点などを、はじめての方にもわかりやすく解説します。
遺言作成の常識が変わる!2025年10月スタートの公正証書遺言デジタル化とは
2025年10月、いよいよ公正証書遺言の作成手続きがオンラインで可能になります。これは、2023年6月に成立した「デジタル社会の実現に向けた関係法律の整備に関する法律」によって実現するもので、手続きの一部または全部を、自宅などからインターネットを通じて行えるようになる大きな制度変更です。
これまでの公正証書遺言は、公証役場に本人が出向き、公証人の面前で作成する必要がありました。しかし今回の制度改正により、パソコンを使ってオンラインで申請や打ち合わせができるほか、ウェブ会議を通じた本人確認や意思表示(口授)も可能になります。さらに、作成された遺言書は電子データ(電磁的記録)として保存され、正本・謄本も希望すれば電子交付が選べます。
この仕組みは、あくまで公証人が関与する「公正証書遺言」の信頼性を維持したまま、手続きの利便性を高めることを目的としたものです。
対面での作成も引き続き可能ですが、オンライン化により、体力的・地理的な理由で公証役場に行くことが難しかった方にとって、大きな後押しになるでしょう。
オンライン作成が実現するまでの背景とメリット
今回の制度改正は、国が進める「行政手続きのデジタル化」の流れの中で実現したものです。
政府は、対面や紙の書類に頼らず、手続きを原則オンラインで完結できるようにする「デジタルファースト」や「リモート社会の実現」といった方針を掲げており、公正証書遺言のオンライン化もその一環として導入されました。
これにより、公正証書遺言の作成は、以下のような点でこれまでよりも便利になります。
■申請(嘱託)のオンライン化
パソコンを使って、公証役場に出向かずに作成の申請が可能に。申請には電子署名を用いるため、本人確認の信頼性も確保されます。
■ウェブ会議による手続き
遺言者が希望し、かつ公証人が相当と認める場合には、ウェブ会議システムを通じて公証人との手続きを進めることが可能です。
■原本の電子データ化
作成された公正証書遺言の原本は、原則として電子データ(電磁的記録)として作成・保存されます。公証役場に安全に保管される点は変わりません。
■証明書(正本・謄本)の電子交付
遺言者が保管する遺言書の控え(正本・謄本)も、希望すれば電子データで受け取ることができます。
【完全ガイド】公正証書遺言をオンラインで作成する具体的なステップ
公正証書遺言をオンラインで作成する場合、以下のようなステップで手続きを進めていきます。基本的な流れは対面の場合と変わりませんが、一部の手続きがオンライン対応となることで、より柔軟かつ効率的に進めることが可能になります。
① 公証役場の選定と事前相談
まずは、オンライン手続きに対応している公証役場を探し、電話やメールなどで事前相談を行います。この際、作成の目的を伝え、手続きの流れや必要書類を確認するのが一般的です。
② オンラインでの申請(嘱託)と必要書類の提出
公証人との事前打ち合わせが済んだら、遺言の作成をオンラインで申請します。申請には電子署名が必要です。あわせて、本人確認書類や財産に関する資料なども、電子データとして提出します。
③ 遺言書案の確認
提出した情報をもとに、公証人が遺言書の原案を作成します。原案はメールなどで共有されるため、内容を十分に確認しましょう。
④ ウェブ会議による本人確認と「口授」
日時を調整したうえで、公証人、遺言者、証人2名以上がウェブ会議を行います。この場では、公証人が遺言者の本人確認を行い、遺言者が遺言の内容を自分の言葉で伝えなければなりません。
⑤ 電子公正証書の作成と交付
すべての手続きが完了すると、公正証書遺言が電子データとして作成・保存されます。遺言者は、正本や謄本を、希望に応じて電子データまたは従来の紙媒体で受け取ることが可能です。
知っておきたい!オンライン作成の注意点
公正証書遺言のオンライン化は非常に便利ですが、すべてのケースで必ずオンライン完結できるわけではありません。
スムーズに進めるためには、いくつかの注意点をあらかじめ理解しておくことが大切です。
■ウェブ会議の利用は絶対ではない
オンラインでの手続きを希望しても、必ずウェブ会議が利用できるわけではありません。利用できるのは「嘱託人が希望し、かつ、公証人が相当と認めるとき」だけ。遺言者の意思能力について慎重な確認が必要な場合などは、公証人の判断で対面での手続きを求められる可能性があります。
■すべての公証役場で一斉に開始されるとは限らない
制度は2025年10月1日頃から施行される見込みですが、システムの整備状況などによっては、当初はオンライン手続きに対応できる公証役場が限られる可能性があります。利用を検討する際は、事前に依頼したい公証役場へ対応状況を確認することが重要です。
■「口授」の重要性は変わらない
オンラインであっても、遺言者が自らの意思で、遺言の趣旨を公証人に口頭で伝える「口授」という要件は必須です。単に公証人が読み上げた案に「はい」と答えるだけでは、口授の要件を満たさないと判断され、遺言が無効になるリスクがあります。
■証人2名以上の立会いは必須
公正証書遺言の作成には、オンラインであっても、証人2名以上の立会いが必要です。なお、推定相続人や受遺者、およびその配偶者・直系血族は証人になることができません。
■電子署名の準備
オンラインで申請(嘱託)を行う際には、電子署名が必要となります。マイナンバーカードに搭載されている電子証明書などを利用することが想定されるため、事前に準備しておくと手続きがスムーズです。
オンライン化で便利になった今、遺言書について司法書士に相談をしてみる
公正証書遺言のオンライン化によって、手続きの物理的な負担は大きく軽減されました。
ただし、手続きが簡単になることと、“納得のいく遺言書”を作れることは、必ずしもイコールではありません。
遺言書で本当に大切なのは、「誰に、どの財産を、どのように残したいのか」というご自身の意思を、法的に有効かつ明確な形で残すことです。
公証人は中立の立場で手続きを進めますが、遺言の内容そのものを提案・助言する役割ではないため、事前に内容をしっかりと考えておく必要があります。
そこで頼りになるのが、相続の専門家である司法書士です。司法書士は、次のようなサポートを通じて、あなたの想いを「確かなかたち」に整えるお手伝いをします。
■遺言内容のコンサルティング
ご自身の希望を丁寧にヒアリングし、法的に問題がなく、将来の紛争を防げるような最適な遺言内容を一緒に検討します。
■煩雑な書類収集の代行
相続関係を証明するための戸籍謄本や、不動産の登記事項証明書など、作成に必要な書類の収集を代行します。
■公証役場との事前調整
公証人との打ち合わせや遺言書案の調整をスムーズに進め、当日の手続きを円滑に進行させます。
■証人の手配
信頼できる証人が見つからない場合、司法書士が証人を引き受けることも可能です。
公正証書遺言のオンライン化は、遺言を残すハードルを大きく下げてくれました。
この機会に、ご自身の人生の集大成として、そしてご家族への大切なメッセージとして、遺言書の作成を前向きに考えてみてはいかがでしょうか。
「何から始めたらよいかわからない」という方も、まずは司法書士にご相談ください。あなたの想いを、きちんと未来へつなげるお手伝いをいたします。
この原稿作成時点(2025年11月2日)では、まだ、遺言を、オンラインで全て完結して作成するには、以下の2点の理由からハードルが高そうです。
1点目は、遺言者と証人2人は、全員同じ場所でZoom等のウェブ会議を行う必要があります。
それぞれの自宅や事務所でという訳にはいかず、全員1か所に集まる必要があります。通常は、専門家の事務所に集まることになると思いますので、平日に仕事の合間に職場でZoomで作成するというニーズには、現状、応えられないと思います。
2点目は、Zoom等のウェブ会議の際、その場所に利害関係人がいないということを、公証人が確認出来る必要があります。
例えば、オープンスペースでウェブ会議を行うと、周囲に利害関係人がいる可能性があり、公証人としては、遺言書の作成に応じられないということになると思います。
通常は、個室で、更に、利害関係人がウェブ会議の際、カメラの死角に隠れることが出来ないと言った状況が必要になると思われ、公証人が事前に現地を確認することも想定されます。通常、そこまでするのであれば、公証人に出張してもらい、その場で遺言書を作成してしまった方が1回で済みますので、上記の様なケースでは、わざわざオンラインで遺言を作成する実益がないかも知れません。
遺言の完全オンライン作成については、今後の動向を注視したいと思います。
2025年12月1日時点での船橋公証役場での運用を追記します。
公正証書遺言は、電子データをメールで受領することも可能になりましたが、予め遺言者からメールで受領する旨を公証役場に申請する必要があります。
今回、公証役場で遺言書を作成し、電子データをCDで受領致しましたが、電子データをメールで受領する旨を記載した紙(書式はまだ定められてないそうです。)に、該当メールアドレスと遺言者の住所氏名を記載し実印で押印することで、メールで受領することも可能です。
電子データをCD又はメールで受領した場合、データはPDFになります。
編集可能なソフト(例えば、Adobe Acrbat)を使用して、署名の検証をする際、『文書の証明の完全性が不明です。』と言ったエラーメッセージが出ることがある様です。その際は、Adobe Acrobat Readerを使用すると、うまく表示される様です。