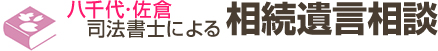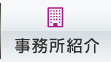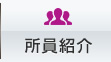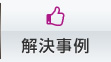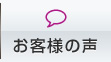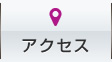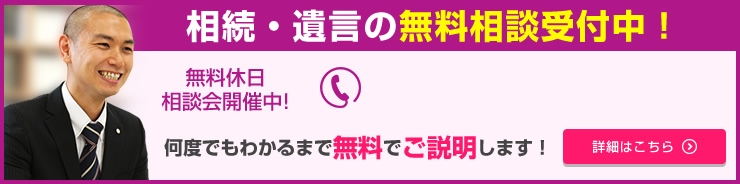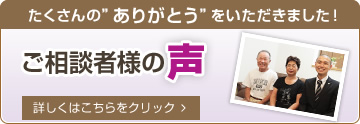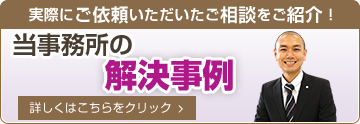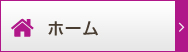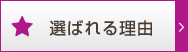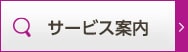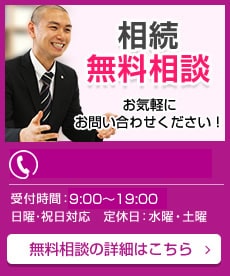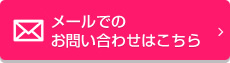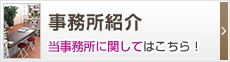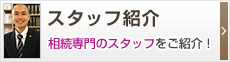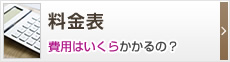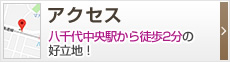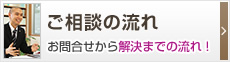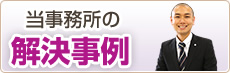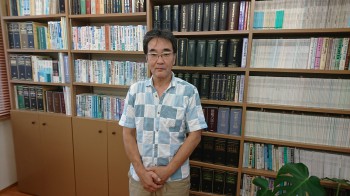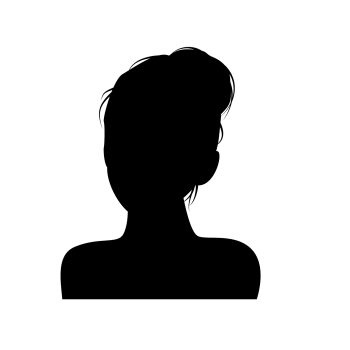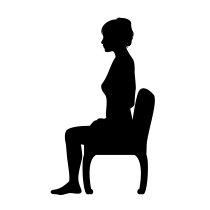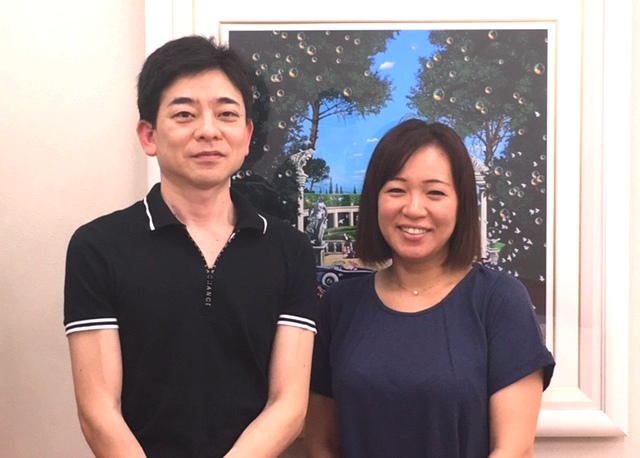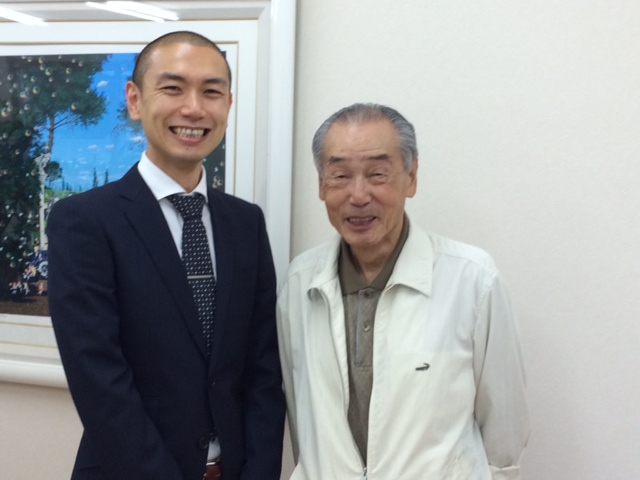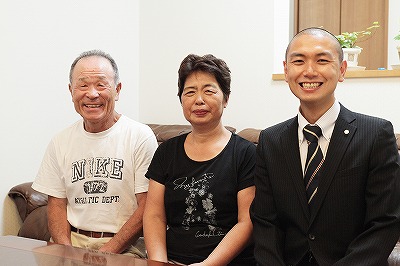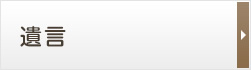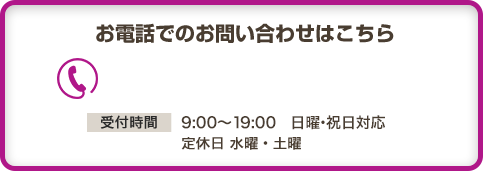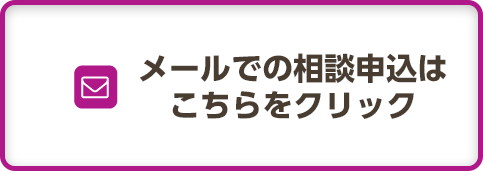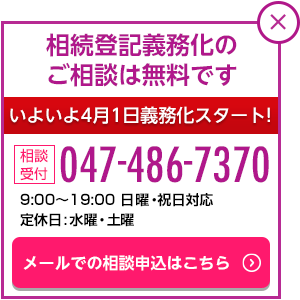死後のSNSの取り扱い、親族にスマホやPCをみられない方法、終活など生前にやっておきたい9つのこと
人はいつか必ず亡くなるものです。将来、死亡したときに備えるには「生前」にさまざまな準備をしておかねばなりません。
たとえば死後にはフェイスブックやツイッターなどのSNSを閉じる準備も必要となるでしょう。スマホやPCの中身の処分方法についても生前の準備が必要です。
この記事ではSNSやスマホ・PCの処分、遺言書やエンディングノートの作成など、生前にやっておきたい相続対策のポイントを9つご紹介します。
終活を意識している方はぜひ参考にしてみてください。
1.SNSの削除
最近ではフェイスブックやツイッターなどのSNSを利用している方が多数います。
死後にアカウントを放置しておくと関わりのあった方にも心配をかけてしまいますし、アカウントが悪用されるおそれもあります。死亡したときにはSNSアカウントが削除されるよう、準備をしておきましょう。
以下では代表的なSNSであるフェイスブックとツイッターをもとに対処方法をお伝えします。
1-1.フェイスブックの場合
フェイスブックの場合「追悼アカウント管理人」の設定をしておくようおすすめします。
追悼アカウント管理人とは、生前に設定しておいて、本人が死亡したときにアカウントの管理や削除を行ってもらう人です。
追悼アカウント管理人を設定しておくと、万一のことがあった際に追悼アカウント管理人にログインしてもらい、最終メッセージを投稿してもらえます。
ただし追悼アカウント管理人は過去の投稿の削除やアカウント自身の削除はできません。
もし死後にフェイスブックのアカウント自体を削除したいなら「アカウント削除」の設定をしておく必要があります。アカウント削除設定をしておくと、友人や家族などから本人の死亡が通知されたとき、フェイスブックアカウントが自動で削除されます。
フェイスブックを利用しているなら、信頼できる人(子どもなど)に追悼アカウント管理人になってもらい、アカウント削除設定もしておくと良いでしょう。
1-2.ツイッターの場合
ツイッターの場合、生前に死後の対応をあらかじめ決めておく機能がありません。(2023年1月20日時点)死亡後には親族などがログインして、プライバシーフォームからツイッター運営へアカウント削除のリクエストを行って審査をしてもらい、アカウントを削除する必要があります。
最終のメッセージなども親族などが本人のアカウントにログインして投稿しなければなりません。死後に伝えたいメッセージがある場合には、あらかじめ信頼できる人へ死後のアカウント管理(最終メッセージ投稿)や削除について依頼しておくと良いでしょう。
ブログなどについても同様です。信頼できる人にIDやパスワードを伝えて死後の処理方法を示し、依頼しておきましょう。
2.スマホやパソコンの中を見られたくない場合の対処方法
世間では、死後にスマホやパソコンの中身を親族などにみられたくない方が多数います。
以下では死後にスマホやパソコンのデータを消去して親族にみられなくする方法をご紹介します。
2-1.パソコンのデータを消去する方法
パソコンの場合、一定期間以上ログインされないとデータが自動削除されるソフトを入れておくとよいでしょう。ただし生前にログインしないで放置するとデータが消えてしまう可能性があるので、長期で家をあけるような際には注意が必要です。
データが消去されるまでの期間は自分で設定できるので、間違えて消してしまわないようにコントロールしましょう。
司法書士などの専門家にあらかじめ依頼しておいて、死後にパソコンデータを消去してもらうことも可能です。死後事務委任などでPCやスマホの処理に対応している事務所を探しましょう。
2-2.スマホを親族にみられない方法
スマホの場合には「指紋認証」や「顔認証」機能を利用しましょう。これらの機能がついていれば、死後に第三者が勝手に中身を見ることができません。
iPhoneの場合、パスコードを11回間違えると全データが自動消去されるように設定することが可能です。(2023年1月20日時点)
より簡単な方法としては、パソコンやスマホの場合、親族の知り得ないパスワードを設定しておけば誰にもログインされずみられずに済みます。
3.葬儀の方法を決めておく
終活として、死後の葬儀の方法を決めておくようおすすめします。
葬儀には費用がかかりますし、急いでやらなければならないのに準備が大変で、相続人に負担がかかるケースも多いからです。また葬儀の方法については自分でも希望をもつ方が多数います。
以上のような理由から、最近では自分で葬儀の方法を決めて予約しておく人が増えているのです。
葬儀の宗派や規模、葬儀会社や段取りなどを決めて、予約しておくと良いでしょう。
4.お墓や埋葬方法を決めておく
最近では、お墓や埋葬方法を生前に決めておく人も多くなっています。
生前にお墓や埋葬方法を決めておくと、相続人が考えなくて済むので負担をかけずに済みます。また自分の希望を実現できるメリットもあるでしょう。
お墓や埋葬方法について例を挙げると、以下のような選択肢があります。
- 先祖代々のお墓に入る
- お墓を買う
- 永代供養してもらう
- 納骨堂にいれてもらう
- 海洋に散骨してもらう
- 樹木葬にしてもらう
- 手元供養
- 宇宙葬
霊園やお寺などに相談に行っても良いですし、ネットでも散骨などさまざまな埋葬やお墓のサービスを見つけられます。価格やサービス内容もさまざまなので、自分にあったものを探してみてください。
5.遺言書を作成する
終活として、必ず遺言書を作成するようおすすめします。遺言書を作成するのは、相続人たちがトラブルを起こさないためです。
遺言書がない場合、法定相続人が話し合って相続方法を決めなければなりません。そうなると、各相続人の意見が合わずにトラブルになるケースが多々あります。特に遺産の中に不動産が含まれていると、誰が取得するか、不動産の評価方法などをめぐって争いになる事例がよくみられます。親の生前には仲の良かった子どもたちでも、親の相続争いをきっかけに絶縁してしまう事例も珍しくありません。
相続トラブルを防ぐには遺言書の作成が有効です。遺言書があれば遺言内容が優先されるので、相続人たちが自分たちで相続方法を決める必要がないからです。「うちの子どもに限って争うはずがない」などと考えずに遺言書を作成しておきましょう。
また遺言書があれば、自分の希望するとおりに遺産を受け継がせられるメリットもあります。たとえば内縁の配偶者などの相続権のない人にも遺贈によって遺産を受け継がせられますし、法定相続分を無視した相続方法もとることができます。
公正証書遺言と自筆証書遺言のどちらが良いか
よく利用される遺言書の方式には自筆証書遺言と公正証書遺言がありますが、これらのうち無効になりにくいのは公正証書遺言です。
公正証書遺言は原本が公証役場で保管されるので、紛失や変造、破棄などのリスクもありません。また公正証書遺言の場合、死後に相続人が検索して調べられるので、せっかく作成した遺言書が発見されないリスクも低減できます。
より確実に死後に意思を実現するには公正証書遺言を作成しておくようおすすめします。
6.エンディングノートを作成する
遺言書と並行して、エンディングノートも作成しておくようおすすめします。
エンディングノートには法的効力はありません。ただし相続人やその他の親族などへ本人の思いや連絡事項を伝えたりするのに便利です。
以下のような内容を書いておくと良いでしょう。
- 財産の内容、金額や保管場所
- 親しい人の連絡先
- 墓守の指名
- 相続の手続きをお願いしたい専門家の指名(司法書士、税理士等)
- 葬儀に呼んでほしい知人等の連絡先
- SNSの管理や削除の方法
- SNS、パソコン、スマホ、ネット銀行やネット証券のIDやパスワードなど
7.遺産の内容を把握する
将来の相続に備えるため、自分が今どのような資産や負債を有しているのか、全容を把握しましょう。把握ができたら、財産目録を作成して、相続人たちに一覧でわかるようにしておくようおすすめします。
遺産の内容を明らかにするのは、死後のトラブルを防止したり財産の散逸を防いだりするためです。死後に遺産の内容が明らかになっていないと、相続人間で「他にも財産があるのではないか」などと互いに疑心暗鬼になってトラブルが生じるケースが少なくありません。
また預金口座などがあっても、財産が発見されないままになってしまうおそれもあります。
生前に財産目録(財産の一覧表)を作成してエンディングノートに記載したり、目録を遺言書に添付したりしましょう。
8.法定相続人や遺留分を把握しておく
次に、法定相続人も把握しておきましょう。
法定相続人とは、民法が定める相続人です。遺言書がない場合には法定相続人が遺産を取得することになります。その場合、法定相続分に応じて相続するのが原則です。遺言書を作成するとしても、本来の法定相続人や法定相続分を把握しておくことは重要です。
遺言書を作成するなら、遺留分の把握も必須となります。遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
遺言によっても遺留分権利者の遺留分を奪うことはできません。遺言書によって遺留分を侵害してしまったら、死後に遺留分権利者が侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行い、相続トラブルにつながってしまうおそれもあります。
遺言書を作成するとしても法定相続人や遺留分についての知識が必要なので、事前に調べておきましょう。わからない場合には司法書士などの専門家に相談するようおすすめします。
8-1.法定相続人になる人
民法の定める法定相続人について、簡単に示します。
- 配偶者は杖に法定相続人になる
配偶者以外の相続人について
- 子どもが第1順位の法定相続人(子どもが先に死亡していたら孫が相続人になる。孫も先に死亡していたらひ孫が相続人になる、以下同様)
- 親が第2順位の法定相続人(親が先に死亡していて祖父母が生きていたら祖父母が相続人になる、祖父母も先に死亡していたら曽祖父母が相続人になる、以下同様)
- 兄弟姉妹が第3順位の法定相続人(兄弟姉妹が先に死亡していたら甥姪が相続人になる。甥姪の子どもは相続人にならない)
8-2.遺留分について
遺留分は、以下の割合になります。
- 親などの直系尊属のみが相続人の場合は3分の1
- 上記以外の場合(配偶者や子どもなどが相続人の場合)は2分の1
上記の割合をそれぞれの遺留分権利者が法定相続分に応じて分配します。
遺留分の計算方法は複雑なので、自信がない場合には司法書士までご相談ください。
9.相続税のシミュレーションと節税対策
遺産額が一定以上あると、相続税がかかります。
死後に突然高額な相続税がかかることが明らかになって相続人が困らないために、生前に相続税のシミュレーションと節税対策を行っておきましょう。
相続税がかかるのは、基本的に遺産額が相続税の基礎控除を超える場合です。超えない場合には相続税はかかりません。
- 相続税の基礎控除=3000万円+法定相続人数×600万円
節税対策方法としては、以下のような手法があります。
- 不動産を購入する
- 不動産を賃貸に出す
- 養子縁組をする
- 生前贈与をする
- 生命保険に加入する(納税資金の準備)
具体的にどのような手法が最適かはケースによって異なります。司法書士が不動産を活用した対処方法をお伝えすることもできますので、よければご相談ください。
まとめ
千葉県のはながすみ司法書士事務所では、相続対策に力を入れて取り組んでいます。相続対策の支援や遺言書作成、不動産の活用のご相談、遺産整理業務や死後事務委任契約など多岐にわたって承っています。死後の相続対策に関心をお持ちの方がおられましたら、お気軽にご相談ください・