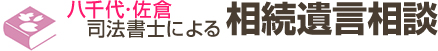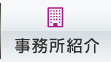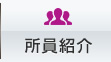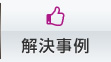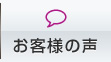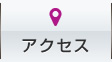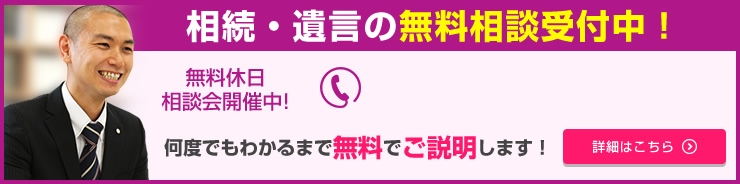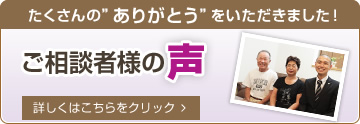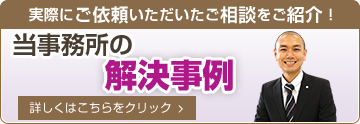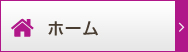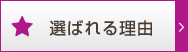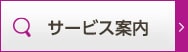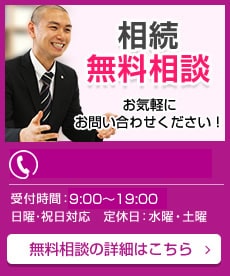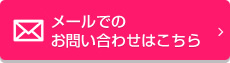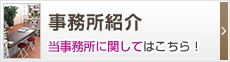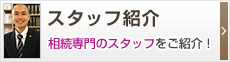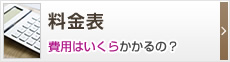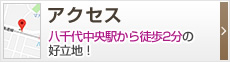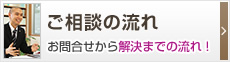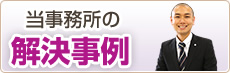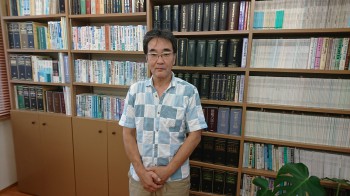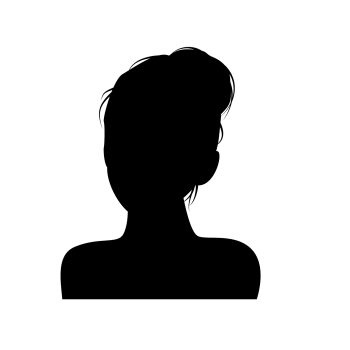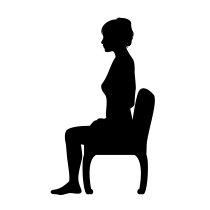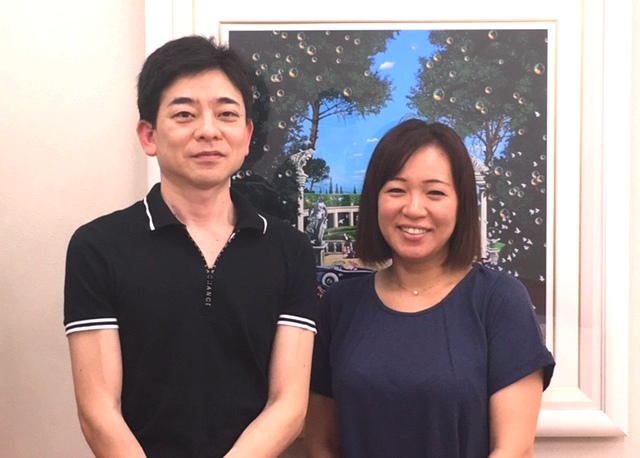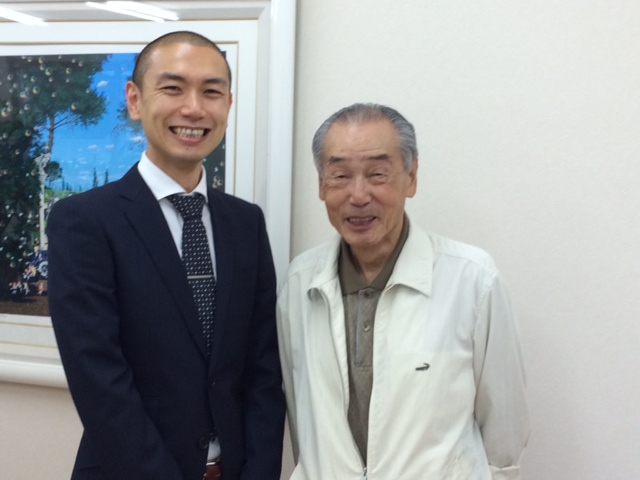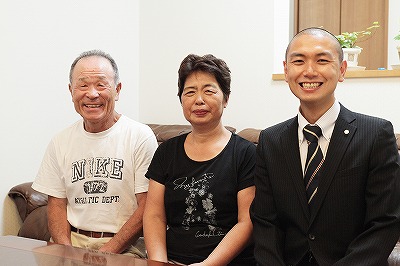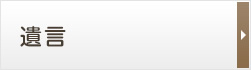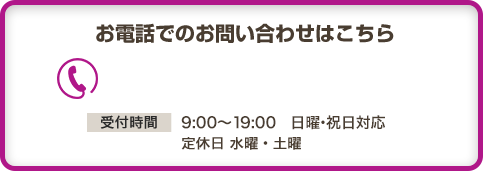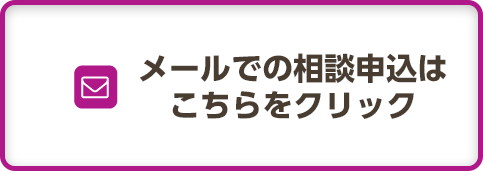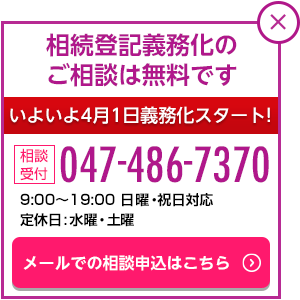【相続と社会貢献】遺贈寄付について
近年、遺産を寄付する「遺贈寄付」という選択をする人が増えています。その背景には、配偶者がすでに亡くなり、子どもも独立している場合や、子どもと疎遠で相続させたくないといった事情があります。また、相続する身内がいない方も、自分の財産を社会のために役立てたいと考えることが多いようです。
手続きをしないままでは、遺産が相続人や国に渡る可能性があります。しかし、特定の団体や社会貢献活動に遺産を活用してもらいたい場合は、生前に遺贈寄付の計画を立てることが大切です。
遺贈寄付を考えても、「どこに寄付すればいいのか」「手続きはどう進めればいいのか」と悩む方も多いでしょう。本記事では、遺贈寄付を行うための手続きや準備のポイントをわかりやすく解説します。
遺贈寄付とは
社会貢献活動や非営利団体に自分の遺産を寄付する仕組みのことを遺贈寄付といいます。
遺贈寄付には、遺言書を用いる「遺贈」と、生前に契約を結ぶ「死因贈与」の2つの方法があります。
「遺贈」は遺言書を作成し、「どの団体に」「どの財産を」寄付するかを明記することで実現します。この方法では、遺言執行者が遺言内容に従い、寄付手続きを進めます。
一方、「死因贈与」は、生前に寄付先と契約を交わし、贈与者が亡くなった後に効力が生じる仕組みです。この方法では、事前に寄付内容を双方で確認し合うため、贈与者の意図を確実に反映することができます。
どちらの方法も、自分の財産を社会のために活用する手段として、近年注目を集めています。
社会貢献以外のメリット
遺贈寄付は社会貢献になるだけでなく、意外なメリットもたくさんあります。ここでは、その魅力をわかりやすくご紹介します。
節税ができる
遺贈寄付を行うことで、相続税の負担を減らすことが可能です。相続税は、基礎控除額を超える財産に課税されますが、遺贈寄付で指定した財産は課税対象外となります。
また、相続人が遺産を相続した後に寄付を行った場合でも、以下の条件をすべて満たせば課税対象から外せます。
- 相続税の申告期限までに寄付する
- 財産をそのままの形で寄付する
- 国が認めた団体に寄付する
これらを活用することで、相続税を抑えつつ社会貢献が可能です。
財産の行き先を決められる
相続人がいない場合、財産は原則として国のものになります。しかし、遺贈寄付を使えば、自分が大切だと思う目的や団体に財産を活用してもらえます。
例えば、自分が応援したいNPOや学校、自分にゆかりのある地域団体に寄付することで、大切な財産を有意義に使うことができます。これにより、財産を無駄にせず、自分の意思を反映できます。
寄付金控除が受けられる
故人が生前に自営業などで確定申告をしていた場合、相続人は相続後に準確定申告をする必要があります。このとき、遺贈寄付を行うと、条件を満たせば寄付金控除が適用されます。
寄付金控除を受ければ、所得税の負担を減らし、実質的に相続財産を増やすことが可能です。これは、相続人にとって大きなメリットとなります。
遺贈寄付の方法
遺贈寄付を行うには、大きく分けて「遺贈」と「死因贈与」の2つの方法があります。それぞれの特徴を理解して、自分の希望に合った方法を選ぶことが大切です。
遺贈とは
遺贈は、遺言書に「誰に何を渡すのか」を記載し、特定の人や団体に遺産を贈る方法です。遺言書がなければ、法定相続人が遺産を相続しますが、遺贈を使えば、相続人以外の団体や親族に財産を渡すことができます。
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2つの方法があります。それとは別に、遺贈に条件を付けることもできます。これを「負担付遺贈」といいます。
それぞれについて簡単に解説します。
包括遺贈
包括遺贈とは、財産全体の一定割合を贈与する方法です。例えば、「全財産の50%をA団体に寄付する」といった形です。この場合、資産だけでなく借金などの負債も引き継がれる点に注意が必要です。
特定遺贈
特定遺贈とは、具体的な財産を指定して渡す方法です。例えば、「この土地をBさんに渡す」といった形です。包括遺贈と違い、負債は引き継がれません。ただし、財産内容が変わった場合には遺言書を更新する必要があるため、定期的に内容を確認することが大切です。
負担付遺贈
遺贈には条件を付けることもできます。「この財産を医療研究に使う」といった条件を付ける場合、それを負担付遺贈と呼びます。条件が守られない場合、相続人が家庭裁判所に遺言の取り消しを求めることも可能です。
死因贈与とは
死因贈与は、贈与者(財産を渡す人)が亡くなった後に効力を発揮する契約です。遺贈が遺言書による一方的な意思表示であるのに対し、死因贈与は贈与者と受贈者(財産を受け取る人)の双方が合意して成立します。
死因贈与では、契約内容に条件を付けることができます。例えば、「生前に介護をしてくれたら自宅を譲る」といった形です。このような条件付きの死因贈与は、負担付死因贈与と呼ばれます。
ただし、贈与者が生前に条件を果たしてもらえなかった場合には契約を取り消すことができます。一方で、受贈者が条件をしっかり果たした場合は、契約の撤回が難しくなります。
遺贈と死因贈与、どちらを選ぶべき?
遺贈と死因贈与を選ぶ際には、それぞれの違いを理解することが重要です。
まず、遺贈は遺言書を作成するだけで成立するため、手続きが簡単で広く利用されています。ただし、遺贈は贈与者が一方的に意思を示すものであり、生前に受け取る側との合意がないため、遺言執行の段階で意図が正しく伝わらないリスクもあります。
一方死因贈与は、贈与者と受贈者が生前に契約を結ぶことで進められる方法です。この方法では、条件を事前に確認し合えるため、贈与者の意図を確実に反映できます。ただし、契約書の作成が必要で、手続きが複雑になる点には注意が必要です。
贈与の目的や財産の内容、関係者の状況を考慮し、自分の意図がより適切に伝わる方法を選ぶことが大切です。
遺贈寄付の進め方
遺贈寄付を行うには、「遺贈」と「死因贈与」の二つの手段があることは先述の通りです。手段の違いによって、遺贈寄付の進め方も変わってきます。
遺贈で寄付をする方法
遺贈を選ぶ場合、遺言書を作成する必要があります。遺言書には以下の3つの種類があります。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分の手で全てを書いて作成する方法です。費用がかからず簡単に作れますが、以下のポイントに注意が必要です。
- 財産目録以外は全て手書き
- 日付と署名を記載
- 押印を忘れない
書き方に不備があると無効になる可能性が高いため、司法書士などの専門家に確認してもらうと安心です。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証人の前で作成する方法です。公証人が内容を確認しながら書類を作成するため、形式上のミスがなく、確実な手続きが可能です。費用はかかりますが、最も信頼性が高い方法としておすすめです。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にしたまま保管できる方法です。作成には公証人や証人が必要で、手続きが複雑になるため利用者は少ないですが、内容を他人に知られたくない場合には有効です。
死因贈与で寄付をする方法
死因贈与を選ぶ場合、寄付先の団体と事前に契約を結ぶ必要があります。契約は口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐため、書面での契約が推奨されます。
死因贈与には、贈与者と受け取る側が契約内容を事前に確認できるというメリットがあります。具体的な条件を設定したい場合や、寄付先との詳細な取り決めを行いたい場合に適した方法です。
遺贈寄付は少額でも可能か?
遺贈寄付は少額から始められる手軽な方法です。「多額の財産が必要」と考える人もいますが、実際にはそうではありません。たとえば、1万円といった少額の寄付でも、その行為自体に大きな価値があります。
少額の寄付でも社会に役立ち、必要としている人々や団体に貢献できます。自分の無理のない範囲で取り組める点が、遺贈寄付の魅力と言えるでしょう。
遺贈寄付で注意すること
遺贈寄付を進めるときは、いくつかの重要な点に注意が必要です。
遺留分に配慮する
遺贈や死因贈与で寄付を進める際には、「遺留分」に気を配る必要があります。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取る権利が保障された財産の割合を指します。具体的な割合は以下の通りです。
- 直系尊属のみが相続人の場合:相続財産の3分の1
- それ以外の場合:相続財産の2分の1
遺贈寄付によって相続人の遺留分が侵害された場合、相続人は寄付先の団体に対して「遺留分侵害額請求」を行うことがあります。このような請求を避けるには、事前に遺留分を十分に考慮した計画を立てることが大切です。
寄付先による相続税の違い
遺贈寄付を活用して相続税を節約するには、寄付先の選び方が重要です。国や地方公共団体、公益法人(社会福祉法人や認定NPO法人など)への寄付は、相続税が課税されません。一方、その他の法人や個人への寄付には相続税がかかります。
こういった事情を加味して、寄付先は慎重に選びましょう。
不動産寄付の注意点
不動産を寄付する場合、そのまま遺贈するのではなく、現金化して寄付する「清算型遺贈」を検討しましょう。不動産をそのまま遺贈すると、時価で譲渡したとみなされ、値上がり益に譲渡所得税が課税される可能性があります。
さらに、譲渡所得税が発生した場合、相続人は相続開始後4か月以内に準確定申告を行い、税金を納めなければなりません。不動産を現金化することで、こうした負担を減らすことができます。
まとめ
遺贈寄付は、自分の財産を社会のために活用できる有意義な方法です。しかし、遺留分や相続税、不動産の扱いなど、注意すべき点がいくつかあります。これらを十分に理解し、適切に対処することで、寄付をスムーズに進めることができます。
遺贈寄付を検討している方は、専門家のサポートを受けることをおすすめします。司法書士に相談すれば、遺言書の作成や手続きの進め方について的確なアドバイスを受けられます。ぜひお気軽に司法書士にご相談ください。