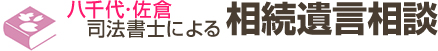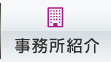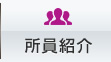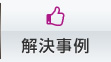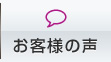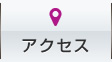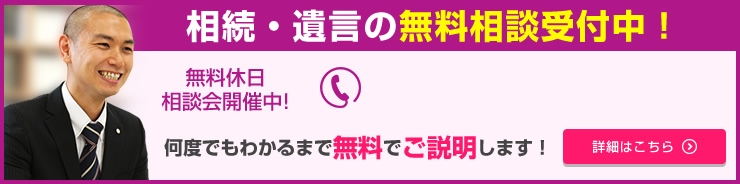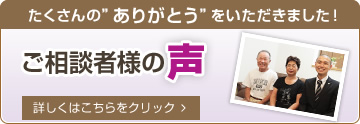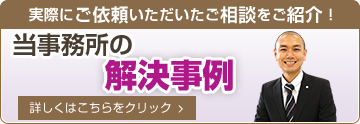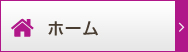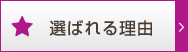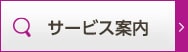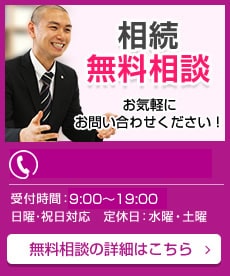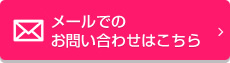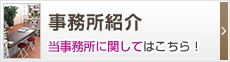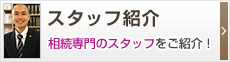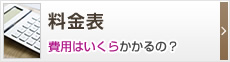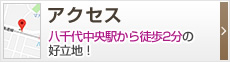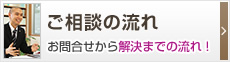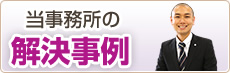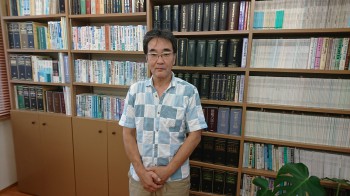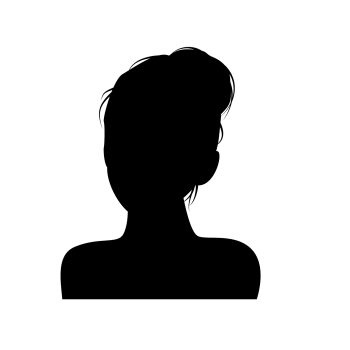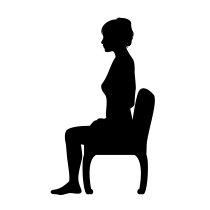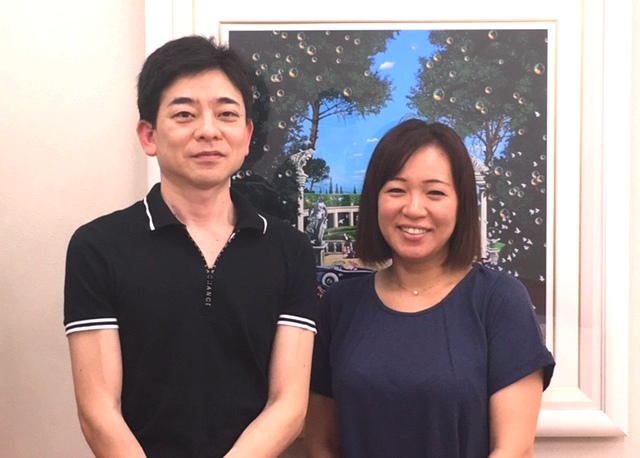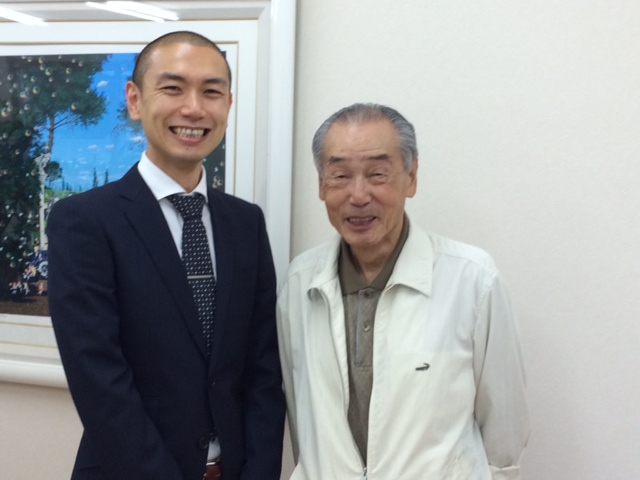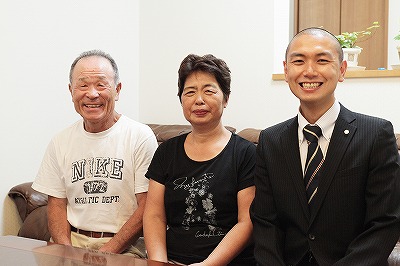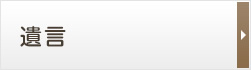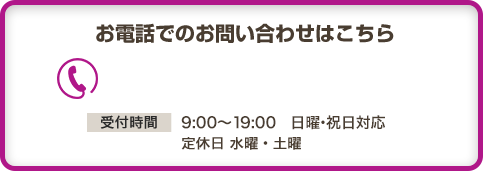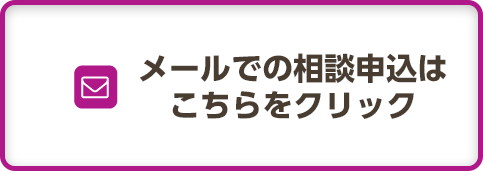【2026年4月開始】個人も法人も不動産所有者は必見! 住所等変更登記の義務化で変わる手続きと注意点

2026年4月、不動産の「住所・氏名(名称)変更登記」が義務になります。これまで任意だった手続きが法改正により義務化され、怠ると最大5万円の過料が科される可能性も。
対象は、すべての不動産所有者。個人も法人も例外ではありません。引越し、結婚、会社の本店移転など、日常的な変化がそのまま「登記ミス」扱いになる時代が、もうすぐやってくるのです。
この記事では、住所等変更登記の義務化の背景から、新たに導入される制度の仕組み、具体的な手続きの流れ、気をつけたい注意点までを、専門家の視点からわかりやすく整理してお伝えします。
2026年4月施行「住所等変更登記の義務化」の背景
今回の法改正の背景にあるのが、いわゆる「所有者不明土地問題」です。これは、登記簿に記載されている住所や氏名が古く、実際の所有者と連絡が取れなくなることが一因と言われています。
所有者が亡くなったあとに相続登記が行われなかったり、引越しや結婚・改名などの際に住所や氏名の変更登記がされなかったりするケースが多く、それが土地の放置や利活用の妨げになっているのです。
もともと住所・氏名の変更登記は任意であり、登記情報が古くてもすぐに大きな不利益が生じるわけではなかったため、後回しにされがちでした。しかしその結果、全国で所有者不明の土地が増加し、公共事業の停滞や空き家問題など、深刻な社会的影響が広がっています。
こうした事態を防ぐために、登記情報を正確に保つことが求められ、今回の法改正で「住所・氏名(名称)変更登記」が義務化されることになったのです。
何が変わる? 「住所等変更登記の義務化」の具体的な内容
2026年4月1日から施行される新制度では、不動産の所有者が住所や氏名(法人の場合は名称や本店所在地)を変更した場合、その内容を登記簿に反映させることが義務となります。
従来は任意だったこの手続きが義務化されることで、登記情報の正確性が保たれ、不動産の適切な管理や利活用が進められるようになることを目的としています。
変更内容の反映方法や、義務に違反した場合の罰則、さらに登記官による職権での変更制度の導入など、主なポイントは以下の通りです。
■登記申請の義務化と申請期限
住所や氏名(名称)に変更があった場合、不動産の所有者は変更日から2年以内に登記申請を行う必要があります。法人の場合は、本店の所在地変更や商号変更などが該当します。
この「2年以内の申請」が守られない場合、罰則の対象となる可能性があります。
■正当な理由なく申請を怠った場合の罰則
期限内に申請を行わず、正当な理由もない場合は、5万円以下の過料が科される可能性があります。
過料とは、行政上のペナルティであり、刑罰ではありませんが、法的義務に違反していることには変わりありません。
■登記官による職権での変更登記制度の導入
変更手続きの負担を軽減し、登記の正確性を確保するため、一定の条件を満たした場合には、登記官が職権で変更登記を行う制度が新たに導入されます。
この制度は、個人と法人で運用方法が異なるため、それぞれ見ていきましょう。
・個人の場合
所有者が登記申請時に生年月日などの検索用情報を提供していると、登記官が定期的に住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)に照会し、住所変更の有無を確認できます。
ただし、変更情報が確認された場合でも、所有者の同意がなければ、登記官が勝手に変更登記を行うことはできません。
そのため、変更情報が確認された場合には、まず本人に確認を取り、同意があれば職権で登記を行います。
・法人の場合
法人の場合は、登記情報に「会社法人等番号」が追加されます。これにより、商業登記システムと不動産登記システムが連携し、本店所在地や名称の変更情報が自動で不動産登記側へ通知される仕組みです。通知を受けた登記官は、法人からの申出がなくても職権で変更登記を行うことができます。
義務化によって生じる影響とペナルティなどの注意点
住所や氏名(法人は名称・本店所在地)の変更登記が義務化されることで、不動産の所有者には新たな責任が発生します。
正しく対応しなかった場合には、過料(行政罰)や手続き上の不利益を受ける可能性もあるため、注意が必要です。
以下に、特に重要なポイントをまとめました。
■申請期限を過ぎた場合は過料の対象に
前述の通り、正当な理由なく2年以内の申請を怠ると、5万円以下の過料の対象となります。「正当な理由」がどのようなケースを指すかについては、今後の具体的な運用で明らかになりますが、基本的には期限内に手続きを行うことが重要です。
■相続登記時の注意点
相続が発生し、亡くなった方(被相続人)名義の不動産を相続登記する場合、登記簿上の被相続人の住所が古い住所のままであっても、その住所変更登記を別途申請する必要はありません。そのまま相続登記の手続きを進めることができます。
■DV被害者等への配慮
DV(ドメスティック・バイオレンス)被害者等で、支援措置を受けている方については、住所変更登記をしなくてもよいとする特例が設けられています。これにより、現在の住所が登記簿に記録されることを防ぐことができます。
住所変更が発生した場合の手続きの流れ
不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合、その変更登記の手続きは、大きく分けて次の2つのパターンがあります。
①所有者自身が申請する方法
②登記官が職権で変更する方法
どちらの方法になるかは、所有者の対応や登録情報の内容によって異なります。以下で、それぞれの手続きの流れについて見ていきましょう。
①所有者自身による申請手続き
所有者自身が登記申請を行う場合は、以下の内容を順に確認し、必要な書類をそろえて申請します。
■申請内容の記載
登記申請書には、変更の内容とその日付を記載します。たとえば住所を移転した場合は、登記原因欄に「住所移転」と明記し、移転日と新しい住所を記載する必要があります。
■添付書類
変更の内容に応じて、以下のような証明書類を添付します。
- 住所変更の場合:住民票や戸籍の附票など、変更前後の住所のつながりが確認できるもの
- 氏名変更の場合:戸籍謄本+住民票など、改姓や改名の事実が記載されたもの
※過去に複数回住所や氏名が変更されている場合でも、複数件に分けて申請する必要はありません。一件の申請で最新の情報に変更できますが、登記簿の情報と現在の情報をつなぐ証明書類がすべて必要になります。
■登録免許税
登録免許税は、原則として不動産1筆(1個)につき1,000円です。住所変更と氏名変更を同時に行っても、まとめて1,000円で申請可能です。ただし、住居表示の実施による住所変更は、非課税とされています。
■注意点
住所や氏名の変更登記をせずに、所有権移転や抵当権の設定など他の登記申請を行うと、申請が却下される可能性があります。変更がある場合は、事前に必ず変更登記を済ませておきましょう。
登記官による職権での変更手続き
2026年4月からは、登記官が公的情報をもとに住所や氏名の変更を行う「職権による変更登記」の制度も始まります。
所有者が手続きに対応できない場合でも、一定の条件を満たせば、登記官の判断で登記情報を更新することが可能です。
この仕組みは、個人と法人で流れが異なるため、それぞれのポイントを見ていきましょう。
■個人(自然人)の場合
個人の場合は、次の手順で登記官による変更手続きが行われます。
- 登記官が、所有者から提供された生年月日などの検索用情報を基に、定期的に住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)に照会し、住所等の変更情報を取得。
- 変更情報を取得した場合、登記官は所有者本人に変更登記を行うことについて確認を取る。
- 所有者から申出(同意)があった場合に限り、登記官は職権で変更登記を行う。
なお、本人への確認と申出を必須とするのは、DV被害者など最新の住所を公示することに支障があるケースや、個人情報保護の観点に配慮するためです。また、海外に居住している所有者は住基ネットで情報を取得できないため、職権による変更登記の対象外となり、自ら申請する必要があります。
■法人の場合
法人には、新たに「会社法人等番号」が登記項目として追加されることになりました。これにより、商業登記システムと不動産登記システムが連携し、本店所在地や名称に変更があった場合、その情報が自動的に通知されるようになります。
通知を受けた登記官は、法人からの申出がなくても職権で変更登記を行うことが可能です。
個人と違って本人確認や同意の手続きは不要なので、よりスムーズに変更登記が行うことができます。
手続きは専門家に相談! 司法書士に依頼するメリット
住所や氏名の変更登記は、自分で手続きを行うこともできますが、書類の内容や登記情報との整合性をしっかり確認する必要があり、慣れていないと意外と手間がかかります。とくに、何度も引越しや改姓をしている場合は、過去の情報とのつながりを示す資料をそろえるだけでも一苦労です。
そうした場面では、登記手続きの専門家である司法書士に相談することで、正確でスムーズな申請が可能になります。書類の不備による差し戻しを防ぎ、無駄な時間や労力を省くことができるのはもちろん、平日に法務局へ出向く手間もかかりません。
また、住所変更だけでなく、相続登記や抵当権の抹消など、他の手続きが必要な場合にもまとめて対応してもらえるのも大きなメリットです。必要なことを一度に整理できるので、あとから「あれもやってなかった」と慌てるリスクも減らせます。
不動産を所有している以上、今回の法改正は誰にとっても無関係ではありません。ご自身の状況を確認し、来るべき施行に備えましょう。ご不明な点や手続きにご不安があれば、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。